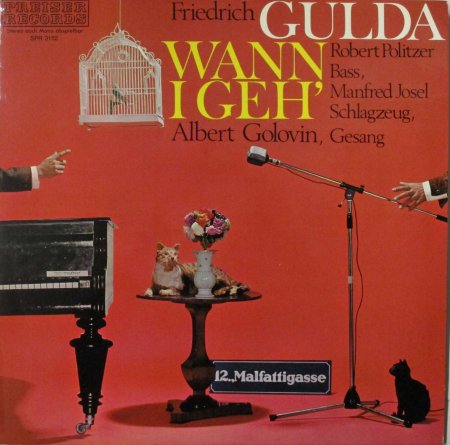гӮёгғ§гғ«гӮёгғҘгғ»гғқгғӘгғ„гӮ§гғ«пјҲGeorges PolitzerгҖҒ1903е№ҙ5жңҲ3ж—Ҙ - 1942е№ҙ5жңҲ23ж—ҘпјүгҒҜгғ•гғ©гғігӮ№гҒ®еҝғзҗҶеӯҰиҖ…гҖҒе“ІеӯҰиҖ…гҖҒе…ұз”Је…ҡе“ЎгҖҒеҜҫзӢ¬гғ¬гӮёгӮ№гӮҝгғігӮ№йҒӢеӢ•е®¶гҖӮгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўпјқгғҸгғігӮ¬гғӘгғјеёқеӣҪгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјйқ©е‘ҪгҒ®еҫҢгҖҒ18жӯігҒ®гҒЁгҒҚгҒ«жёЎд»ҸгҖӮгӮҪгғ«гғңгғігғҢеӨ§еӯҰгҒ§е“ІеӯҰгӮ’е°Ӯж”»гҒ—гҖҒеӨ§еӯҰж•ҷжҺҲиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮгғӘгӮ»гҒ§ж•ҷйһӯгӮ’еҹ·гӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҺеҝғзҗҶеӯҰгҒ®еҹәзӨҺжү№еҲӨгҖҸгӮ’еҹ·зӯҶгҒ—гҖҒеҫ“жқҘгҒ®жҠҪиұЎзҡ„гҒӘеҝғзҗҶеӯҰгҖҒгҖҢдёүдәәз§°гҒ®еҝғзҗҶеӯҰгҖҚгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҢдёҖдәәз§°гҒ®дё»дҪ“гҖҚгҒ®гҖҢгғүгғ©гғһгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөгҒ«гӮҲгӮӢе…·дҪ“зҡ„гҒӘеҝғзҗҶеӯҰгӮ’жҸҗе”ұгҒ—гҒҹгҖӮ1929е№ҙгҒ«е…ұз”Је…ҡгҒ«е…Ҙе…ҡгҒ—гҖҒиіҮж–ҷеҸҺйӣҶгғ»дҪңжҲҗгҖҒиӘҝжҹ»гғ»з ”究гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒҶгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒе…ҡгҒ®ж•ҷиӮІж©ҹй–ўгҖҢеҠҙеғҚеӨ§еӯҰгҖҚгҒ§гҖҢгғһгғ«гӮҜгӮ№дё»зҫ©и¬ӣеә§гҖҚгӮ’жӢ…еҪ“гҖӮжІЎеҫҢгҒ«еҸ—и¬ӣз”ҹгҒ®гғҺгғјгғҲгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰз·ЁзәӮгҒ•гӮҢгҒҹгҖҺе“ІеӯҰгҒ®еҹәжң¬еҺҹзҗҶгҖҸгҒҜйӮҰиЁігҖҺе“ІеӯҰе…Ҙй–ҖгҖҸгҒЁгҒ—гҒҰзүҲгӮ’йҮҚгҒӯгҒҹгҖӮгғҠгғҒгӮ№гғ»гғүгӮӨгғ„еҚ й ҳдёӢгҒ§зҹҘиӯҳдәәгғ»еӨ§еӯҰж•ҷе“ЎгҒ«гӮҲгӮӢеҜҫзӢ¬гғ¬гӮёгӮ№гӮҝгғігӮ№йҒӢеӢ•гӮ’зөҗжҲҗгҒ—гҖҒгҖҺиҮӘз”ұеӨ§еӯҰгҖҸиӘҢгҖҒгҖҺиҮӘз”ұжҖқжғігҖҸиӘҢгӮ’ең°дёӢеҮәзүҲгҖӮгғ•гғ©гғігӮ№иӯҰеҜҹзү№еҲҘзҸӯгҒ«йҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгҖҒгғүгӮӨгғ„и»ҚгҒ«еј•гҒҚжёЎгҒ•гӮҢгҒҹеҫҢгҖҒеҮҰеҲ‘гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
з”ҹж¶Ҝ
иғҢжҷҜ
гӮёгғ§гғ«гӮёгғҘпјҲгӮёгӮ§гғ«гӮёпјүгғ»гғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜ1903е№ҙ5жңҲ3ж—ҘгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўпјқгғҸгғігӮ¬гғӘгғјеёқеӣҪгҒ®гғҠгӮёгғҙгӮЎгғјгғ©гғүпјҲNagyvГЎradгҖҒзҸҫгғ«гғјгғһгғӢгӮўиҘҝйғЁгғҲгғ©гғігӮ·гғ«гғҙгӮЎгғӢгӮўең°ж–№гғ“гғӣгғ«зңҢгҒ®зңҢйғҪгӮӘгғ©гғҮгӮўпјүгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгҖӮзҲ¶гӮёгғЈгӮігғ–гҒҜгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўпјқгғҸгғігӮ¬гғӘгғјеёқеӣҪгҒ®еӣҪ家公еӢҷе“ЎгҒ§гҒӮгӮӢз”ЈжҘӯеҢ»гҒ§гҖҒеҪ“жҷӮгҒҜзөҗж ёзҷӮйӨҠжүҖгҒ®жүҖй•·гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒиҒ·еӢҷдёҠгҖҒе°ҸиҰҸжЁЎгҒӘе·ҘжҘӯйғҪеёӮгӮ„иҫІжқ‘гҒ«еҮәеҗ‘гҒ„гҒҰе·Ҙе ҙзөҢе–¶иҖ…гӮ„иҫІең°жүҖжңүиҖ…гҒ®иҰҒи«ӢгҒ«еҝңгҒҳгӮӢгҖҢдҪ“еҲ¶еҒҙгҖҚгҒ®з«Ӣе ҙгҒ«гҒӮгӮҠгҖҒгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜж—©гҒҸгҒӢгӮүиҫІж°‘гғ»еҠҙеғҚиҖ…гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢзҲ¶гҒ®жЁ©еЁҒдё»зҫ©зҡ„гҒӘж…ӢеәҰгҒ«еҸҚжҠ—гҒ—гҒҹгҖӮжҜҚгӮ®гӮјгғ©гҒҜгғҰгғҖгғӨзі»гҒ®е®¶еәӯгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгҖҒдҝқйҷәдјҡзӨҫгҒ«еӢӨеӢҷгҒ—гҖҒжј”еҠҮгӮ„зҫҺиЎ“гҒ«й–ўеҝғгҒҢж·ұгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гӮ»гӮІгғүпјҲгғҸгғігӮ¬гғӘгғјпјүгҒ®дёӯзӯүж•ҷиӮІж©ҹй–ўпјҲдёӯеӯҰж Ўгғ»й«ҳзӯүеӯҰж ЎпјүгҒ«е…ҘеӯҰгҒ—гҒҹгҖӮе„Әз§ҖгҒӘеӯҰз”ҹгҒ§гҖҒеӯҰз”ҹ委員дјҡгҒ®е§”е“Ўй•·гҒЁгҒ—гҒҰжҙ»иәҚгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјж°‘дё»е…ұе’ҢеӣҪзӢ¬з«ӢпјҲ1918е№ҙ11жңҲ16ж—ҘпјүзӣҙеҫҢгҒ«зөҗжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгғҸгғігӮ¬гғӘгғје…ұз”Је…ҡгҒ®йқ©е‘ҪгӮ’ж”ҜжҢҒгҒҷгӮӢжҙ»еӢ•гҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҰйҖҖеӯҰеҮҰеҲҶгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒ1919е№ҙгҖҒ16жӯігҒ§гӮ»гӮІгғүеёӮеәҒиҲҺгҒ«еӢӨеӢҷгҒ—гҖҒе…ұз”Је…ҡгҒ«е…Ҙе…ҡгҒ—гҒҹгҖӮ
е…ұз”Је…ҡгҒ®жҢҮе°ҺиҖ…гӮҜгғігғ»гғҷгғјгғ©гҒҢзҺҮгҒ„гӮӢгғҸгғігӮ¬гғӘгғјйқ©е‘ҪгӮ’ж”ҜжҢҒгҒ—гҖҒе…ұз”Је…ҡгҒҢж”ҝжЁ©гӮ’жҺҢжҸЎгҒ—гҒҰгғҸгғігӮ¬гғӘгғји©•иӯ°дјҡе…ұе’ҢеӣҪгҒҢжҲҗз«ӢгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜйқ©е‘Ҫзҫ©еӢҮи»ҚгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгғ»гғ«гғјгғһгғӢгӮўжҲҰдәүгҒ§еӨ§ж•—гӮ’е–«гҒ—гҖҒйқ©е‘ҪгҒҜеӨұж•—гҒ«зөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҖӮгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒ®жҒҜеӯҗгҒ§з”»е®¶гғ»еҪ«еҲ»е®¶гҒ®гғҹгӮ·гӮ§гғ«гғ»гғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜгҖҒ2013е№ҙгҒ«зҷәиЎЁгҒ—гҒҹзҲ¶гғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒ®дјқиЁҳгҖҺгӮёгғ§гғ«гӮёгғҘгғ»гғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒ®3еәҰгҒ®жӯ»гҖҸгҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҢеҪјгҒ®жңҖеҲқгҒ®жӯ»гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁиӘһгӮӢгҖӮ
гғ–гғҖгғҡгӮ№гғҲйғҠеӨ–гғ©гғјгӮігӮ·гғҘгғ‘гғӯгӮҝгҒ®е…¬з«Ӣй«ҳж ЎгҒ«з·Ёе…ҘгҒ—гҖҒгҒҷгҒ§гҒ«зҝ’еҫ—гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгғүгӮӨгғ„иӘһгҖҒиӢұиӘһгҒ«еҠ гҒҲгҖҒз•ҷеӯҰгҒ«еӮҷгҒҲгҒҰгғ•гғ©гғігӮ№иӘһгӮ’еӯҰгӮ“гҒ гҖӮзҝҢе№ҙгҖҒгғ–гғҖгғҡгӮ№гғҲгҒ®й«ҳзӯүеӯҰж ЎгҒ§е“ІеӯҰгӮ’еӯҰгҒігҖҒ1921е№ҙгҒ«дёӯзӯүж•ҷиӮІгӮ’дҝ®дәҶгҒ—гҒҹгҖӮ
жёЎд»Ҹ
еҗҢе№ҙгҖҒ18жӯігҒ®гҒЁгҒҚгҒ«гҖҒгӮҰгӮЈгғјгғіпјҲгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўпјүгҒ«ж•°йҖұй–“ж»һеңЁгҒ—гҒҹеҫҢгҒ«жёЎд»ҸгҖӮгӮҰгӮЈгғјгғігҒ§гҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгғ•гғ©гғігӮ№гҒ§гҒҜгҒҫгҒ гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©зҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮёгғјгӮҜгғ гғігғҲгғ»гғ•гғӯгӮӨгғҲгҖҒгғ•гӮ§гғ¬гғігғ„гӮЈгғ»гӮ·гғЈгғјгғігғүгғ«гӮүгҒ®зІҫзҘһеҲҶжһҗгҒ®гӮ»гғҹгғҠгғјгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҖҒеҫҢгҒ®з ”究гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гғүгӮӨгғ„иӘһгҒ®и‘—жӣёгӮ’иіје…ҘгҒ—гҒҹгҖӮеҗҢе№ҙгҖҒгӮҪгғ«гғңгғігғҢеӨ§еӯҰгҒ«е…ҘеӯҰгҖӮгғ—гғӯгғҶгӮ№гӮҝгғігғҲеӯҰз”ҹеҚ”дјҡпјҲAssociation des Г©tudiants protestantsпјүгҒ®ж”ҜжҸҙгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гӮҪгғ«гғңгғігғҢеӨ§еӯҰгҒ®жі•еӯҰж•ҷжҺҲгҒ§гӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўпјқгғҸгғігӮ¬гғӘгғјеёқеӣҪз ”з©¶гӮ’е°Ӯй–ҖгҒЁгҒҷгӮӢгӮ·гғЈгғ«гғ«гғ»гӮўгӮӨгӮјгғігғһгғігҒ®еҸ–гӮҠиЁҲгӮүгҒ„гҒ§е…¬ж•ҷиӮІзңҒгҒ®еҘЁеӯҰйҮ‘гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒзҝҢ1922е№ҙеәҰгҒ«гҒҜгҖҒгғҷгғ«гӮ®гғјзі»гғҰгғҖгғӨдәәйҮ‘иһҚжҘӯиҖ…гғ’гғ«гӮ·гғҘз”·зҲөпјҲMaurice de HirschпјүгҒҢеүөиЁӯгҒ—гҒҹгғҰгғҖгғӨжӨҚж°‘еҚ”дјҡгҒ®еҘЁеӯҰйҮ‘гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ
гӮҪгғ«гғңгғігғҢеӨ§еӯҰгҒ§еҗҲзҗҶдё»зҫ©гҒ®ж•°зҗҶе“ІеӯҰиҖ…гғ¬гӮӘгғігғ»гғ–гғ©гғігӮ·гғҘгғҙгӮЈгғғгӮҜгҒ«её«дәӢгҒ—гҒҹгҖӮгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜгӮ«гғігғҲгҖҒгғҮгӮЈгғүгғӯгҖҒгғҙгӮ©гғ«гғҶгғјгғ«гҖҒгғҮгӮ«гғ«гғҲгӮүзҗҶжҖ§дё»зҫ©гғ»е•“и’ҷдё»зҫ©гғ»еҗҲзҗҶдё»зҫ©е“ІеӯҰгҒ®еҹәзӨҺгӮ’зҜүгҒ„гҒҹе“ІеӯҰиҖ…гҒӢгӮүеӨҡгҒҸгӮ’еӯҰгҒігҖҒе“ІеӯҰз•Ңгғ»еӨ§еӯҰгҒ®е“ІеӯҰж•ҷиӮІгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰеӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝеҠӣгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮўгғігғӘгғ»гғҷгғ«гӮҜгӮҪгғігҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜдёҖиІ«гҒ—гҒҰжҖқжғізҡ„гҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡж”ҝжІ»зҡ„гҒӘиҰізӮ№гҒӢгӮүгӮӮжү№еҲӨзҡ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹпјҲеҫҢиҝ°пјүгҖӮеӯҰдҪҚеҸ–еҫ—гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘеҝғзҗҶеӯҰгҒ®и©ҰйЁ“гӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒзІҫзҘһеҢ»еӯҰз ”з©¶гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰдёӯеҝғзҡ„гҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒҶгӮөгғіпјқгӮҝгғігғҢз—…йҷўгҒ®и¬ӣзҫ©гӮ’еҸ—и¬ӣгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зөҢйЁ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒ•гӮүгҒ«еҝғзҗҶеӯҰгҒёгҒ®й–ўеҝғгӮ’ж·ұгӮҒгҖҒгғ•гғӯгӮӨгғҲз ”з©¶гӮ’йҖІгӮҒгҒҹгҖӮ1923е№ҙгҒ«е“ІеӯҰгҒ®еӯҰеЈ«еҸ·гӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҝҢе№ҙгҒ«й«ҳзӯүз ”з©¶еӯҰдҪҚпјҲDiplГҙme d'Г©tudes supГ©rieuresпјүгӮ’еҸ–еҫ—гҒ—гҒҹгҖӮ
еҗҢе№ҙ2жңҲ17ж—ҘгҒ«гҖҒи¬ӣзҫ©гҒ§зҹҘгӮҠеҗҲгҒЈгҒҹе„Әз§ҖгҒӘеӯҰз”ҹгӮ«гғҹгғјгғҰгғ»гғҺгғӢгғјпјҲCamille NonyпјүгҒЁзөҗе©ҡгҒ—гҖҒзҝҢ1924е№ҙгҒ«з¬¬дёҖеӯҗгӮёгғЈгғігҒҢиӘ•з”ҹгҖӮгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜеҗҢе№ҙ12жңҲ21ж—ҘгҒ«гғ•гғ©гғігӮ№еӣҪзұҚгӮ’еҸ–еҫ—гҒ—гҒҹгҖӮ1927е№ҙ2жңҲ16ж—ҘгҒ«гҒҜ第дәҢеӯҗгӮ»гӮ·гғ«гҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҫҢгҖҒгӮ«гғҹгғјгғҰгҒЁйӣўе©ҡгҒ—гҖҒ1931е№ҙ3жңҲ5ж—ҘгҒ«еҫҢгҒ«гғһгӮӨгғ»гғқгғӘгғ„гӮ§гғ«пјҲMaГҜ PolitzerпјүгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгғһгғӘгғјгғ»гғһгғҒгғ«гғүгғ»гғ©гӮ«гғ«гғүпјҲMarie Mathilde LarcadeпјүгҒЁеҶҚе©ҡгҒ—гҖҒдёҖеӯҗгғҹгӮ·гӮ§гғ«гӮ’гӮӮгҒҶгҒ‘гҒҹгҖӮгғһгӮӨгҒҜеҠ©з”Је©ҰгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒз—…гҒ«еҖ’гӮҢгҒҰд»•дәӢгӮ’ж–ӯеҝөгҒ—гҖҒеҫҢгҒ«е…ұз”Је…ҡе“ЎгҒЁгҒ—гҒҰгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒЁжҙ»еӢ•гӮ’е…ұгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
ж•ҷжӯҙ
1925е№ҙ10жңҲгҒ«гҖҒгӮўгғӘгӮЁзңҢгғ гғјгғ©гғігҒ®гғӘгӮ»гғ»гғҶгӮӘгғүгғјгғ«пјқгғүпјқгғҗгғігғҙгӮЈгғ«гҒ®е“ІеӯҰгҒ®д»Јз”Ёж•ҷе“ЎгҒЁгҒ—гҒҰиөҙд»»гҖӮзҝҢ1926е№ҙгҒ«е“ІеӯҰгҒ®еӨ§еӯҰж•ҷжҺҲиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҒ—гҒҹеҫҢгҖҒгғһгғігӮ·гғҘзңҢгӮ·гӮ§гғ«гғ–гғјгғ«гҒ®гғӘгӮ»гҒ«иөҙд»»гҒ—гҒҹгҖӮ1928е№ҙ5жңҲгҒӢгӮүзҝҢ29е№ҙ7жңҲгҒҫгҒ§е…өеҪ№гҒ«жңҚгҒ—гҖҒйҷӨйҡҠеҫҢгҒ«гӮ·гӮ§гғ«гғ–гғјгғ«гҒ®гғӘгӮ»гҒ«еҫ©иҒ·гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҗҢеғҡгҒЁгҒ®ж”ҝжІ»зҡ„гҒӘиҰӢи§ЈгҒ®еҜҫз«ӢгҒӢгӮүгғӯгғҜгғјгғ«пјқгӮЁпјқгӮ·гӮ§гғјгғ«зңҢгғҙгӮЎгғігғүгғјгғ гҒ«з•°еӢ•гҒ•гҒӣгӮүгӮҢгҒҹгҖӮгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜгҒ“гҒ®еҫҢгҖҒ1930е№ҙгҒӢгӮүгӮҰгғјгғ«зңҢгӮЁгғҙгғ«гғјпјҲгғҺгғ«гғһгғігғҮгӮЈгғјең°еҹҹеңҸпјүгҒ®гғӘгӮ»гҖҒ1938е№ҙгҒӢгӮүгғ‘гғӘйғҠеӨ–гӮөгғіпјқгғўгғјгғ«пјқгғҮпјқгғ•гӮ©гғғгӮ»пјҲгғҙгӮЎгғ«пјқгғүпјқгғһгғ«гғҢзңҢпјүгҒ®гғӘгӮ»гғ»гғһгғ«гӮ»гғ©гғіпјқгғҷгғ«гғҶгғӯгҒ§е“ІеӯҰгӮ’ж•ҷгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒйҖұгҒ«ж•°ж—ҘгҒ®еӢӨеӢҷгҒ§гҖҒеҫҢиҝ°гҒ®еҠҙеғҚеӨ§еӯҰгҒ®ж•ҷе“ЎгӮ’е…јд»»гҒ—гҖҒеҗҢжҷӮгҒ«гҒҫгҒҹеҹ·зӯҶжҙ»еӢ•гӮ„ж”ҝжІ»жҙ»еӢ•гӮ’зІҫеҠӣзҡ„гҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҺеҝғзҗҶеӯҰгҒ®еҹәзӨҺжү№еҲӨгҖҸ
д»ЈиЎЁдҪңгҖҺеҝғзҗҶеӯҰгҒ®еҹәзӨҺжү№еҲӨгҖҸпјҲйӮҰйЎҢгҖҺзІҫзҘһеҲҶжһҗгҒ®зөӮз„ү - гғ•гғӯгӮӨгғҲгҒ®еӨўзҗҶи«–жү№еҲӨгҖҸпјүгҒ®еҹ·зӯҶгӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгӮ·гӮ§гғ«гғ–гғјгғ«гҒ®гғӘгӮ»гҒ«еӢӨеӢҷгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ1928е№ҙгҒ«еҲҠиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮжң¬жӣёгҒ§гҒҜгҖҒгғ•гғӯгӮӨгғҲгҒ®зІҫзҘһеҲҶжһҗгӮ’йҷӨгҒ„гҒҰгҖҒеҫ“жқҘгҒ®еҝғзҗҶеӯҰгҒҢжҠҪиұЎзҡ„гҒӘеҝғзҗҶеӯҰгҖҒгҖҢдёүдәәз§°гҒ®еҝғзҗҶеӯҰгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жү№еҲӨгҒ—гҖҒгҖҢе…·дҪ“зҡ„еҝғзҗҶеӯҰгҖҚгҖҒгҖҢдёҖдәәз§°гҒ®дё»дҪ“гҖҠз§ҒпјҲjeпјүгҖӢгҒ®еҝғзҗҶеӯҰгҖҚгӮ’жҸҗе”ұгҒ—гҖҒеҗҢжҷӮгҒ«гҒҫгҒҹгҖҒгғ•гғӯгӮӨгғҲгҒ®зІҫзҘһеҲҶжһҗгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒз„Ўж„ҸиӯҳгҒ®жҰӮеҝөгӮ’жү№еҲӨгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒ«д»ЈгӮҸгӮӢдәәй–“еҖӢдәәгҒ®гҖҢгғүгғ©гғһпјҲdrameпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдё»иҰізҡ„еҝғзҗҶеӯҰгҒЁе®ўиҰізҡ„еҝғзҗҶеӯҰгҒ®зөұеҗҲгӮ’и©ҰгҒҝгҒҹгҖӮжң¬жӣёгҒҜгғ•гғӯгӮӨгғҲгҒ®зІҫзҘһеҲҶжһҗгҒ®зҙ№д»ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒгҒ“гӮҢгӮ’е“ІеӯҰзҡ„гҒӘиҰізӮ№гҒӢгӮүжү№еҲӨзҡ„гҒ«иӘӯгҒҝзӣҙгҒҷдҪңжҘӯгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҫҢгҒ®гҖҢе®ҹеӯҳдё»зҫ©зҡ„гғ»зҸҫиұЎеӯҰзҡ„еӮҫеҗ‘гӮ’гӮӮгҒӨе“ІеӯҰгғ»еҝғзҗҶеӯҰгғ»зІҫзҘһеҢ»еӯҰгҖҚгҖҒгҒЁгӮҠгӮҸгҒ‘гҖҒгӮўгғ«гғҒгғҘгӮ»гғјгғ«гҖҒгғ©гӮ«гғігӮүгҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒ®жІЎеҫҢгҒҫгӮӮгҒӘгҒҸгҖҒеҪјгҒ®з ”究гҒ®еҶҚи©•дҫЎгӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҒҹгҒ®гӮӮгғ©гӮ«гғігҒЁгғЎгғ«гғӯгғјгғ»гғқгғігғҶгӮЈгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
еӯҰиЎ“йӣ‘иӘҢ
гҖҺе“ІеӯҰгҖҸгҖҒгҖҺзІҫзҘһгҖҸгҖҒгҖҺе…·дҪ“зҡ„еҝғзҗҶеӯҰи©•и«–гҖҸгҖҒгҖҺгғһгғ«гӮҜгӮ№дё»зҫ©и©•и«–гҖҸ
гғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜжҲҰй–“жңҹгҒ®гғ•гғ©гғігӮ№жҖқжғігҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҹиӨҮж•°гҒ®йӣ‘иӘҢгҒ®еүөеҲҠгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеҪ“еҲқгҒҜгҖҒгӮҪгғ«гғңгғігғҢеӨ§еӯҰгҒ§еҮәдјҡгҒЈгҒҹгғһгғ«гӮҜгӮ№дё»зҫ©з ”究иҖ…гҖҒзү№гҒ«еҫҢгҒ®дҪң家гғ”гӮЁгғјгғ«гғ»гғўгғ©гғігӮёгғҘгҖҒе“ІеӯҰиҖ…гӮўгғігғӘгғ»гғ«гғ•гӮ§гғјгғҙгғ«гҖҒзҝ»иЁіе®¶гғҺгғ«гғҷгғјгғ«гғ»гӮ®гғҘгғҶгғ«гғһгғігӮүгҒЁгҒ®жҙ»еӢ•гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ1924е№ҙ3жңҲгҒ«гҒҫгҒҡгҖҺе“ІеӯҰпјҲPhilosophiesпјүгҖҸиӘҢгӮ’еүөеҲҠгҒ—гҒҹгҖӮеҗҢиӘҢгҒҜи©©дәәгғ»з”»е®¶гҒ®гғһгғғгӮҜгӮ№гғ»гӮёгғЈгӮігғ–гҒ®ж”ҜжҸҙгӮ’еҫ—гҒҰгҖҒгғһгғ«гӮҜгӮ№дё»зҫ©гҒЁгғ•гғӯгӮӨгғҲгҒ®зІҫзҘһеҲҶжһҗгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгӮ·гғҘгғ«гғ¬гӮўгғӘгӮ№гғ гҒ®иӢҘжүӢдҪң家гӮёгғЈгғігғ»гӮігӮҜгғҲгғјгҖҒгғ«гғҚгғ»гӮҜгғ«гғҙгӮ§гғ«гҖҒгғ”гӮЁгғјгғ«гғ»гғүгғӘгғҘгғ»гғ©гғ»гғӯгӮ·гӮ§гғ«гҖҒгӮёгғҘгғӘгӮўгғігғ»гӮ°гғӘгғјгғігҖҒгғ•гӮЈгғӘгғғгғ—гғ»гӮ№гғјгғқгғјгӮүгӮӮеҜ„зЁҝгҒ—гҖҒгғўгғ©гғігӮёгғҘгҒҢз·ЁйӣҶй•·гӮ’еӢҷгӮҒгҒҹгҖӮ
гҖҺе“ІеӯҰгҖҸиӘҢгҒ®дё»е®°иҖ…гӮүгҒҜгҖҒ1925е№ҙ7жңҲгҒ«дҪң家гӮўгғігғӘгғ»гғҗгғ«гғ“гғҘгӮ№гҒҢеӣҪйҡӣеҸҚжҲҰгғ»е№іе’ҢйҒӢеӢ•гҖҢгӮҜгғ©гғ«гғҶгҖҚгҒ®дёҖз’°гҒЁгҒ—гҒҰе…ұз”Је…ҡгҒ®ж©ҹй–ўзҙҷгҖҺгғӘгғҘгғһгғӢгғҶгҖҸгҒ§гғӘгғјгғ•жҲҰдәүеҸҚеҜҫгӮ’е‘јгҒігҒӢгҒ‘гӮӢгҒЁгҖҒгӮўгғігғүгғ¬гғ»гғ–гғ«гғҲгғігҖҒгғ«гӮӨгғ»гӮўгғ©гӮҙгғігӮүгӮ·гғҘгғ«гғ¬гӮўгғӘгӮ№гғҲгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гғӘгғјгғ•жҲҰдәүеҸҚеҜҫеЈ°жҳҺгҖҢгҒҫгҒҡйқ©е‘ҪгӮ’гҖҒгҒқгҒ—гҒҰеёёгҒ«йқ©е‘ҪгӮ’гҖҚгҒ«зҪІеҗҚгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®е…ұеҗҢеЈ°жҳҺгҒҜгҖҺгғӘгғҘгғһгғӢгғҶгҖҸзҙҷпјҲ1925е№ҙ9жңҲ21ж—Ҙд»ҳпјүгҒЁгҖҺгӮ·гғҘгғ«гғ¬гӮўгғӘгӮ№гғ йқ©е‘ҪгҖҸиӘҢ第5еҸ·пјҲеҗҢе№ҙ10жңҲ15ж—Ҙд»ҳпјүгҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’ж©ҹгҒ«гҖҒе…ұеҗҢеЈ°жҳҺгҒ«зҪІеҗҚгҒ—гҒҹгҖҺе“ІеӯҰгҖҸиӘҢгҒ®дё»е®°иҖ…гҒЁгӮ·гғҘгғ«гғ¬гӮўгғӘгӮ№гғҲгҒҜе…ұз”Је…ҡе“ЎгҒЁжҙ»еӢ•гӮ’е…ұгҒ«гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒ1927е№ҙгҒ«гғ–гғ«гғҲгғігҖҒгӮўгғ©гӮҙгғігҖҒгӮЁгғӘгғҘгӮўгғјгғ«гҖҒгғҗгғігӮёгғЈгғһгғігғ»гғҡгғ¬гӮүгӮ·гғҘгғ«гғ¬гӮўгғӘгӮ№гғҲгҒҢе…ұз”Је…ҡгҒ«е…Ҙе…ҡгҒ—гҖҒ1929е№ҙгҒ«гҒҜгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҖҒгғ«гғ•гӮ§гғјгғҙгғ«гӮүгҒҢе…Ҙе…ҡгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®й ғгҖҒй«ҳзӯүеё«зҜ„еӯҰж ЎгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҖҒе“ІеӯҰгҒ®еӨ§еӯҰж•ҷжҺҲиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҒ—гҒҹдҪң家гғқгғјгғ«гғ»гғӢгӮ¶гғігӮӮе…Ҙе…ҡгҒ—гҖҒгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҖҒгғ«гғ•гӮ§гғјгғҙгғ«гӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒҷгӮӢгғһгғ«гӮҜгӮ№дё»зҫ©иҖ…гҒ®жҙ»еӢ•гҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҺе“ІеӯҰгҖҸиӘҢгҒҜ第5гғ»6еҗҲдҪөеҸ·гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰзөӮеҲҠгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒеҫҢз¶ҡиӘҢгҒЁгҒ—гҒҰ1926е№ҙгҒ«гҖҺзІҫзҘһпјҲLвҖҷEspritпјүгҖҸиӘҢгӮ’еүөеҲҠгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҗҢиӘҢгҒҜ2еҸ·еҲҠиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒҝгҒ§зөӮеҲҠгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜ1929е№ҙгҒ«еҪјиҮӘиә«гҒҢжҸҗе”ұгҒҷгӮӢгҖҢе…·дҪ“зҡ„еҝғзҗҶеӯҰгҖҚгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®йӣ‘иӘҢгҖҺе…·дҪ“зҡ„еҝғзҗҶеӯҰи©•и«–пјҲLa Revue de psychologie concrГЁteпјүгҖҸгӮ’еүөеҲҠгҒ—гҒҹгҖӮ
гғ—гғҒгғ–гғ«е“ІеӯҰгғ»е“ІеӯҰзҡ„жЁ©еЁҒгҒ®жү№еҲӨ
еҗҢгҒҳе№ҙгҒ«еҶҚгҒігғ«гғ•гӮ§гғјгғҙгғ«гҖҒгғўгғ©гғігӮёгғҘгҖҒгӮ®гғҘгғҶгғ«гғһгғігҒЁгҖҺгғһгғ«гӮҜгӮ№дё»зҫ©и©•и«–пјҲRevue marxisteпјүгҖҸиӘҢгӮ’еүөеҲҠгҒ—гҖҒгғӢгӮ¶гғігҒ®гҒ»гҒӢгҖҒеҠҙеғҚзӨҫдјҡеӯҰгҒ®жҸҗе”ұиҖ…гӮёгғ§гғ«гӮёгғҘгғ»гғ•гғӘгғјгғүгғһгғігӮүгҒҢеҸӮеҠ гҒ—гҒҹгҖӮжң¬иӘҢгҒҜгғ•гғ©гғігӮ№гҒ§жңҖеҲқгҒ®гғһгғ«гӮҜгӮ№дё»зҫ©зҗҶи«–гҒ®з ”究иӘҢгҒ§гҖҒгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜеүөеҲҠеҸ·гҒ«гғ•гӮ§гғғгғӘгӮҜгӮ№гғ»гӮўгғ«гғҺгғ«гғҲпјҲFГ©lix ArnoldпјүгҒ®зӯҶеҗҚгҒ§гғ¬гғјгғӢгғігҒ®гҖҺе”Ҝзү©и«–гҒЁзөҢйЁ“жү№еҲӨи«–гҖҸгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁҳдәӢгӮ’жҺІијүгҖӮдёҖж–№гҖҒгҖҺе…·дҪ“зҡ„еҝғзҗҶеӯҰи©•и«–гҖҸиӘҢгҒ«гҒҜгғ•гғ©гғігӮҪгғҜгғ»гӮўгғ«гғјгӮЁпјҲFranГ§ois ArouetпјүгҒ®зӯҶеҗҚгҒ§гҖҢе“ІеӯҰеӨ©еӣҪгғҷгғ«гӮҜгӮҪгғідё»зҫ©гҒ®зөӮз„үгҖҚгӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®и«–ж–ҮгҒҜжІЎеҫҢ1947е№ҙгҒ«гҖҺгғҷгғ«гӮҜгӮҪгғідё»зҫ© - е“ІеӯҰзҡ„ж¬әзһһгҖҸгҒЁгҒ—гҒҰе…ұз”Је…ҡеҮәзүҲеұҖгҒӢгӮүеҶҚеҲҠгҒ•гӮҢгҖҒгҒ•гӮүгҒ«д»–гҒ®йӣ‘иӘҢгҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгҒҹи«–ж–ҮгӮ„ж—ўеҲҠгҒ®и«–йӣҶгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгӮӢи«–ж–ҮгӮ’з·ЁйӣҶгҒ—гҒҰ2013е№ҙгҒ«еҲҠиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҺгғҷгғ«гӮҜгӮҪгғігӮүгҒ«жҠ—гҒ—гҒҰ - е“ІеӯҰзҡ„и‘—дҪң 1924-1939е№ҙгҖҸгҒ«еҶҚйҢІгҒ•гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜгҖҒзҗҶжҖ§дё»зҫ©гӮ„е”Ҝзү©и«–гҒ®з«Ӣе ҙгҒӢгӮүгғҷгғ«гӮҜгӮҪгғігҒ®е”Ҝеҝғи«–гӮ’жү№еҲӨгҒ—гҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғҷгғ«гӮҜгӮҪгғігҖҒгғ–гғ©гғігӮ·гғҘгғҙгӮЈгғғгӮҜгӮүгӮ’еҗ«гӮҖгҖҢзҸҫд»ЈгҒ®гӮ№гӮігғ©еӯҰжҙҫгҖҚгҒ®гҖҢйҒҺеәҰгҒ«ж·ұйҒ гҒӘгҖҚе“ІеӯҰгӮ’гғ—гғҒгғ–гғ«е“ІеӯҰгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮеӣҪ家гҒ«еҚұйҷәгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒҷгӮҲгҒҶгҒӘпјҲгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гғ—гғӯгғ¬гӮҝгғӘгӮўйқ©е‘ҪгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘпјүзңҹгҒ®е•ҸйЎҢи§ЈжұәгӮ’еӣһйҒҝгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒе•ҸйЎҢгҒ®еҜҫиұЎзҜ„еӣІгӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҖҢжҠҪиұЎзҡ„гҖҚгҒ§гҖҢж·ұйҒ гҖҚгҒӘи§ЈжұәгӮ’жҸҗе”ұгҒҷгӮӢгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҢжӯЈзўәгҒ•гӮ’зҠ зүІгҒ«гҒ—гҒҰе®үе…ЁжҖ§гӮ’е„Әе…ҲгҒҷгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гғ—гғҒгғ–гғ«зҡ„гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҖҢиіӘж–ҷгҒ®гҒӘгҒ„е“ІеӯҰгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁдё»ејөгҒҷгӮӢгҖӮгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜгҒ“гҒ“гҒ§гҖҒж”ҝжІ»зҡ„гҒӘиҰізӮ№гҒӢгӮүеӨ§еӯҰгҒ®е“ІеӯҰж•ҷиӮІгӮ„е“ІеӯҰзҡ„жЁ©еЁҒгӮ’жү№еҲӨгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜ1932е№ҙгҒ«гғӢгӮ¶гғігҒҢжҠ—иӯ°ж–ҮгҖҺз•ӘзҠ¬гҒҹгҒЎгҖҸгҒ§гғ–гғ©гғігӮ·гғҘгғҙгӮЈгғғгӮҜгӮ’гҖҢгғ–гғ«гӮёгғ§гғҜжҖқжғігӮ’жҢҜгӮҠгҒӢгҒ–гҒҷгӮҪгғ«гғңгғігғҢгҒ®з•ӘзҠ¬гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰз—ӣзғҲгҒ«жү№еҲӨгҒ—гҒҹгҒ®гҒЁеҗҢгҒҳз«Ӣе ҙгҒӢгӮүгҒ®жү№еҲӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
ж”ҝжІ»жҙ»еӢ•
е…ұз”Јдё»зҫ©гҒ®зҹҘиӯҳдәәгҖҒе…ҡжҙ»еӢ•
1932е№ҙ3жңҲ17ж—ҘгҒ«еӣҪйҡӣйқ©е‘ҪдҪң家еҗҢзӣҹ (UIER) гҒ®гғ•гғ©гғігӮ№ж”ҜйғЁгҒЁгҒ—гҒҰйқ©е‘ҪдҪң家иҠёиЎ“家еҚ”дјҡгҒҢзөҗжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒзҝҢ1933е№ҙ7жңҲгҒ«ж©ҹй–ўиӘҢгҖҺгӮігғҹгғҘгғјгғігҖҸгҒҢеүөеҲҠгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮйқ©е‘ҪдҪң家иҠёиЎ“家еҚ”дјҡзөҗжҲҗжҷӮгҒ®дјҡе“ЎгҒҜдҪң家80дәәгҖҒиҠёиЎ“家120дәәгҖҒгҒҶгҒЎе…ұз”Је…ҡе“ЎгҒҢ36дәәгҒ§гҖҒгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҖҒгғӢгӮ¶гғігҒ®гҒ»гҒӢгҖҒгғ–гғ«гғҲгғігҖҒгӮўгғ©гӮҙгғігҖҒгӮҜгғ«гғҙгӮ§гғ«гҖҒгғҡгғ¬гҖҒгғӯгғҷгғјгғ«гғ»гғҮгӮ№гғҺгӮ№гҖҒгғһгғғгӮҜгӮ№гғ»гӮЁгғ«гғігӮ№гғҲгӮүгҒ®гӮ·гғҘгғ«гғ¬гӮўгғӘгӮ№гғҲгҖҒгӮўгғігғүгғ¬гғ»гғһгғ«гғӯгғјгҖҒгӮўгғігғүгғ¬гғ»гӮёгғғгғүгҖҒгҒ•гӮүгҒ«жҲҰй–“жңҹгҒ®еҸҚжҲҰгғ»е№іе’ҢйҒӢеӢ•гӮ’дё»е°ҺгҒ—гҒҹгғӯгғһгғігғ»гғӯгғ©гғігҖҒгӮўгғігғӘгғ»гғҗгғ«гғ“гғҘгӮ№гӮүгҒҢеҸӮеҠ гҒ—гҖҒгҖҺгғӘгғҘгғһгғӢгғҶгҖҸзҙҷгҒ®з·ЁйӣҶй•·гҒ§дҪң家гҒ®гғқгғјгғ«гғ»гғҙгӮЎгӮӨгғӨгғіпјқгӮҜгғјгғҒгғҘгғӘгӮЁгҒҢдәӢеӢҷеұҖй•·гӮ’еӢҷгӮҒгҒҹгҖӮгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜгҖҺгғӘгғҘгғһгғӢгғҶгҖҸзҙҷгӮ„гҖҺгӮігғҹгғҘгғјгғігҖҸиӘҢгҒ«гӮӮеҜ„зЁҝгҒ—гҖҒе…ұз”Је…ҡгҒ®жҙ»еӢ•гҒ§йҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«дјҙгҒЈгҒҰе“ІеӯҰгғ»еҝғзҗҶеӯҰгҒ®з ”究гҒӢгӮү次第гҒ«йҒ гҒ–гҒӢгӮҠгҖҒгғ«гғ•гӮ§гғјгғҙгғ«гӮүгҒЁгҒ®жұәиЈӮгҒ®еҺҹеӣ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеҪјгҒҜгғӢгӮ¶гғігҒ«гҖҢеүҚиЎӣгҒҜгҒҠгҒ—гҒҫгҒ„гҒ гҖҚгҒЁжҳҺиЁҖгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгғ«гғ•гӮ§гғјгғҙгғ«гҒҜгҖҒ1930е№ҙд»ЈгҒ®гғ•гғ©гғігӮ№гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғһгғ«гӮҜгӮ№дё»зҫ©гҒҜ1гҒӨгҒ®еӯҰе•ҸгҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜгҖҢе…ҡжҙҫзҡ„гҒ§дё»зҫ©гҒ«ж®үгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒ§гҒҚгӮӢиҒ–дәәгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәәй–“гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҝғзҗҶеӯҰиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒӮгӮҢгҒ»гҒ©жүҚиғҪгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҚгҖҒгҒқгӮҢгӮ’е…ұз”Је…ҡгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«ж”ҫжЈ„гҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҒЁиҝ°жҮҗгҒҷгӮӢгҖӮ
е…Ҙе…ҡеҫҢгҒ«гҒҫгҒҡзөұдёҖеҠҙеғҚз·ҸеҗҢзӣҹпјҲCGTUпјүгҒ®гӮёгғҘгғӘгӮўгғігғ»гғ©гӮ«гғўгғігҒӢгӮүгҒ®иҰҒи«ӢгҒ§иіҮж–ҷз®ЎзҗҶеұҖгҒ«еӢӨеӢҷгҒ—гҖҒе…ұз”Је…ҡгҒЁеҠҙеғҚз·ҸеҗҢзӣҹгҒ®жҙ»еӢ•гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«иіҮж–ҷгӮ’еҸҺйӣҶгҒ—гҖҒеҗҢеұҖиІ¬д»»иҖ…гҒ®гӮўгғ«гғҷгғјгғ«гғ»гғҙгӮЎгӮөгғјгғ«гҒ«иӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҖҒ1933е№ҙгҒӢгӮүж”ҝжІ»еұҖгҒ§ж”ҝзӯ–жұәе®ҡгҒ«й–ўгӮҸгӮӢиіҮж–ҷгҒ®еҸҺйӣҶгҒЁдҪңжҲҗгҖҒгҒҠгӮҲгҒідёӯеӨ®е§”е“ЎдјҡгҒ®гӮёгғЈгғғгӮҜгғ»гғҮгғҘгӮҜгғӯгҒӢгӮүгҒ®дҫқй јгҒ§гҖҒгғ’гғҲгғ©гғјеҶ…й–ЈжҲҗз«ӢеүҚеҫҢгҒ®гғүгӮӨгғ„е…ұз”Је…ҡгҒ®жҙ»еӢ•гҒ«й–ўгҒҷгӮӢиіҮж–ҷгӮ„жҲҗз«ӢзӣҙеҫҢгҒ®гғүгӮӨгғ„е…ұз”Је…ҡе“ЎгӮЁгғ«гғігӮ№гғҲгғ»гғҶгғјгғ«гғһгғігҒ®йҖ®жҚ•гҒ«й–ўгҒҷгӮӢиіҮж–ҷгӮ’еҸҺйӣҶгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒйҮҚиҰҒгҒӘд»»еӢҷгӮ’ж¬ЎгҖ…гҒЁиЁ—гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
еҠҙеғҚеӨ§еӯҰгҖҒе…ҡеҶ…гҒ®ж•ҷиӮІз ”究жҙ»еӢ•
1932е№ҙгҒ«гғҗгғ«гғ“гғҘгӮ№гҒЁгғӯгғһгғігғ»гғӯгғ©гғігҒ®жҸҗжЎҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе…ұз”Је…ҡзі»гҒ®ж•ҷиӮІж©ҹй–ўгҒЁгҒ—гҒҰеҠҙеғҚеӨ§еӯҰпјҲL'UniversitГ© ouvriГЁreпјүгҒҢеүөиЁӯгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҖҒ1935е№ҙеәҰгҒ®гҖҢгғһгғ«гӮҜгӮ№дё»зҫ©и¬ӣеә§гҖҚгӮ’жӢ…еҪ“гҒ—гҖҒ1937е№ҙгҒ«и¬ӣзҫ©еҶ…е®№гӮ’з·ЁйӣҶгҒ—гҒҹеҗҢеҗҚгҒ®гҖҺгғһгғ«гӮҜгӮ№дё»зҫ©и¬ӣеә§гҖҸгҒҢе…ұз”Је…ҡеҮәзүҲеұҖгҒӢгӮүеҲҠиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒжІЎеҫҢ1946е№ҙгҒ«гҒ“гҒ®и¬ӣзҫ©гҒ®еҸ—и¬ӣз”ҹгҒ®гғҺгғјгғҲгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҖҺе“ІеӯҰгҒ®еҹәжң¬еҺҹзҗҶгҖҸпјҲгҖҢе“ІеӯҰгҒ®и«ёе•ҸйЎҢгҖҚгҖҒгҖҢе“ІеӯҰзҡ„е”Ҝзү©и«–гҖҚгҖҒгҖҢеҪўиҖҢдёҠеӯҰгҒ®з ”究гҖҚгҖҒгҖҢејҒиЁјжі•гҒ®з ”究гҖҚгҖҒгҖҢеҸІзҡ„е”Ҝзү©и«–гҖҚгҖҒгҖҢејҒиЁјжі•зҡ„е”Ҝзү©и«–гҒЁгӮӨгғҮгӮӘгғӯгӮ®гғјгҖҚгҒ®дә”йғЁж§ӢжҲҗпјүгҒҢеҲҠиЎҢгҒ•гӮҢгҖҒжң¬жӣёгҒ®йӮҰиЁігҖҺе“ІеӯҰе…Ҙй–ҖгҖҸгҒҜ1952е№ҙгҒ«еҲқзүҲгҒҢеҲҠиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹеҫҢгҖҒ1974е№ҙгҒҫгҒ§зүҲгӮ’йҮҚгҒӯгҒҹпјҲи‘—жӣёеҸӮз…§пјүгҖӮгҒ•гӮүгҒ«е…ұз”Је…ҡж•ҷиӮІж©ҹй–ўгҒ®иІ¬д»»иҖ…гӮЁгғҶгӮЈгӮЁгғігғҢгғ»гғ•гӮЎгӮёгғ§гғігҒӢгӮүгҒ®дҫқй јгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҠҙеғҚеӨ§еӯҰгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғ‘гғӘйғҠеӨ–гҒ®гӮёгғҘгғҢгғҙгӮЈгғӘгӮЁпјҲгӮӘгғјпјқгғүпјқгӮ»гғјгғҢзңҢпјүгҒ®еҲқзӯүж•ҷиӮІж©ҹй–ўгҖҒж¬ЎгҒ„гҒ§гӮўгғ«гӮҜгӮӨгғҰпјҲгғҙгӮЎгғ«пјқгғүпјқгғһгғ«гғҢзңҢпјүгҒ®дёӯеӨ®ж•ҷиӮІж©ҹй–ўгҒ§гӮӮе“ІеӯҰгӮ’ж•ҷгҒҲгҒҹгҖӮ
дёҖж–№гҖҒгғўгғјгғӘгӮ№гғ»гғҲгғ¬гғјгӮәжӣёиЁҳй•·гҒҜгҖҒзҹҘиӯҳдәәгҒ®е…ҡе“ЎгӮ’е…ҡгҒ®жҙ»еӢ•гҒ«иіҮгҒҷгӮӢз ”з©¶жҙ»еӢ•гҒ«жҗәгӮҸгӮүгҒӣгҖҒгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜгҖҒе…ҡдё»еӮ¬гҒ®гғҮгӮ«гғ«гғҲгҒ®гҖҺж–№жі•еәҸиӘ¬гҖҸеҮәзүҲпјҲ1637е№ҙпјү300е№ҙиЁҳеҝөдәӢжҘӯгҒ®дјҒз”»гҖҒеҗҢгҒҳеҠҙеғҚеӨ§еӯҰгҒ®ж•ҷе“ЎгҒ§зү©зҗҶеӯҰиҖ…гҒ®гӮёгғЈгғғгӮҜгғ»гӮҪгғӯгғўгғігҒЁгҒ®гӮЁгғігӮІгғ«гӮ№гҒ®гҖҺиҮӘ然гҒ®ејҒиЁјжі•гҖҸгҒ®е…ұиЁігҖҒе”Ҝзү©и«–з ”з©¶гӮ°гғ«гғјгғ—гҒ®зөҗжҲҗгҒӘгҒ©гҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®з ”究дјҡгҒҜе·ҘжҘӯзү©зҗҶеҢ–еӯҰй«ҳзӯүе°Ӯй–ҖеӨ§еӯҰгҒ®зү©зҗҶеӯҰиҖ…гғқгғјгғ«гғ»гғ©гғігӮёгғҘгғҙгӮЎгғігҒ®з ”究е®ӨгҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҖҒз ”з©¶жҲҗжһңгҒҜгҖҒгғ©гғігӮёгғҘгғҙгӮЎгғігҒЁгғһгғ«гӮҜгӮ№дё»зҫ©е“ІеӯҰиҖ…гғ»ж”ҝжІ»жҙ»еӢ•е®¶гҒ®гӮёгғ§гғ«гӮёгғҘгғ»гӮігғӢгӮӘгҒҢ1939е№ҙгҒ«еүөеҲҠгҒ—гҒҹгғһгғ«гӮҜгӮ№дё»зҫ©гҒ®зҙ№д»ӢгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®еӯҰиЎ“йӣ‘иӘҢгҖҺжҖқжғігҖҸпјҲеӯЈеҲҠиӘҢпјүгҒ«зҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮеҗҢиӘҢеүөеҲҠеҸ·жҺІијүгҒ®гғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒ®гҖҢе“ІеӯҰгҒЁзҘһи©ұгҖҚгҒҜгҖҒеӣҪ家зӨҫдјҡдё»зҫ©гғүгӮӨгғ„еҠҙеғҚиҖ…е…ҡе“Ўгғ»еҸҚгғҰгғҖгғӨдё»зҫ©гҒ®зҗҶ論家гӮўгғ«гғ•гғ¬гғјгғҲгғ»гғӯгғјгӮјгғігғҷгғ«гӮҜгӮ’жү№еҲӨгҒҷгӮӢиЁҳдәӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ第2еҸ·гҒ«гҖҢеҗҲзҗҶдё»зҫ©гҒЁгҒҜдҪ•гҒӢгҖҚгӮ’жҺІијүгҒ—гҒҹгҖӮгғӯгғјгӮјгғігғҷгғ«гӮҜжү№еҲӨгҒҜгҒ“гҒ®еҫҢгҖҒ第дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰдёӯгҒ®ең°дёӢеҮәзүҲжҙ»еӢ•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮз¶ҷз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢпјҲеҫҢиҝ°пјүгҖӮ
еӨ§еӯҰж•ҷе“Ўгғ»зҹҘиӯҳдәәгҒ®еҜҫзӢ¬гғ¬гӮёгӮ№гӮҝгғігӮ№йҒӢеӢ•
гҖҺиҮӘз”ұеӨ§еӯҰгҖҸ
1939е№ҙ8жңҲ23ж—ҘгҒ«зӢ¬гӮҪдёҚеҸҜдҫөжқЎзҙ„гҒҢз· зөҗгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҖҒ8жңҲ25ж—ҘгҖҒгғҖгғ©гғҮгӮЈгӮЁеҶ…й–ЈгҒҜе…ұз”Је…ҡгҒ®з¬¬дёҖж©ҹй–ўзҙҷгҖҺгғӘгғҘгғһгғӢгғҶгҖҸгҖҒйқ©е‘ҪдҪң家иҠёиЎ“家еҚ”дјҡгҒ®гҖҺгӮігғҹгғҘгғјгғігҖҸиӘҢгҖҒгӮўгғ©гӮҙгғігҒҢз·ЁйӣҶй•·гӮ’еӢҷгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҖҺгӮ№гғ»гӮҪгғҜгғјгғ«пјҲд»ҠеӨңпјүгҖҸзҙҷгҒӘгҒ©гҖҒе…ұз”Је…ҡгҒ®гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еҲҠиЎҢзү©гӮ’зҷәзҰҒеҮҰеҲҶгҒ«гҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҖҒйӣҶдјҡгӮ„е®Јдјқжҙ»еӢ•гӮӮзҰҒжӯўгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒгҖҺгғӘгғҘгғһгғӢгғҶгҖҸзҙҷгҒ гҒ‘гҒҢд»ҘеҫҢгҖҒгғ‘гғӘи§Јж”ҫгҒ®1944е№ҙгҒҫгҒ§ең°дёӢеҮәзүҲгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеҫҢиҝ°гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е…ұз”Је…ҡдё»е°ҺгҒ®еҜҫзӢ¬гғ¬гӮёгӮ№гӮҝгғігӮ№йҒӢеӢ•гҒ®дёҖз’°гҒЁгҒ—гҒҰеӨҡгҒҸгҒ®ең°дёӢж–°иҒһгғ»йӣ‘иӘҢгҒҢеҚ°еҲ·гғ»й…ҚеёғгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
еҗҢе№ҙ9жңҲгҒ«гғүгӮӨгғ„гҖҒж¬ЎгҒ„гҒ§гӮҪйҖЈгҒҢгғқгғјгғ©гғігғүгҒ«дҫөж”»гҒ—гҖҒ第дәҢж¬ЎеӨ§жҲҰгҒҢеӢғзҷәгҖӮгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜеӢ•е“ЎгҒ•гӮҢгҖҒйҷёи»ҚеЈ«е®ҳеӯҰж ЎгҒ®зөҢзҗҶйғЁгҒ«дјҚй•·гҒЁгҒ—гҒҰй…ҚеұһгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮзӢ¬д»Ҹдј‘жҲҰеҚ”е®ҡз· зөҗеҫҢгҒ«еҫ©е“ЎгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮҪгғӯгғўгғігҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒе•“и’ҷжҖқжғігғ»зҗҶжҖ§дё»зҫ©гҒ®ж“Ғиӯ·гҒ—гҖҒи’ҷжҳ§дё»зҫ©гҒЁй—ҳгҒҶгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеӨ§еӯҰж•ҷе“Ўгғ»зҹҘиӯҳдәәе…ұз”Је…ҡе“ЎгҒ®еҜҫзӢ¬гғ¬гӮёгӮ№гӮҝгғігӮ№йҒӢеӢ•гӮ’зөҗжҲҗгҒ—гҖҒгғүгӮӨгғ„иӘһж•ҷеё«гҒ®гӮёгғЈгғғгӮҜгғ»гғүгӮҜгғјгғ«гҒҢеҸӮеҠ гҒ—гҒҹгҖӮ3дәәгҒҜгҒҫгҒҡгҒ“гҒ®йҒӢеӢ•гҒ®дёҖз’°гҒЁгҒ—гҒҰгҖҺиҮӘз”ұеӨ§еӯҰпјҲL'UniversitГ© libreпјүгҖҸиӘҢгӮ’ең°дёӢеҮәзүҲгҒ—гҒҹгҖӮеҪ“еҲқгҒҜ1940е№ҙ10жңҲ30ж—ҘгҒ«еүөеҲҠеҸ·гӮ’еҲҠиЎҢгҒҷгӮӢдәҲе®ҡгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеҗҢж—ҘгҖҒ1934е№ҙгҒ«зөҗжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹеҸҚгғ•гӮЎгӮ·гӮәгғ зҹҘиӯҳдәәзӣЈиҰ–委員дјҡеүҜ委員長гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгғ©гғігӮёгғҘгғҙгӮЎгғігҒҢгӮІгӮ·гғҘгӮҝгғқгҒ«йҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгҖҒгӮөгғігғҶеҲ‘еӢҷжүҖгҒ«жӢҳз•ҷгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ11жңҲ8ж—ҘгҖҒгӮігғ¬гғјгӮёгғҘгғ»гғүгғ»гғ•гғ©гғігӮ№еүҚгҒ§е…ұз”Јдё»зҫ©гҒ®еӯҰз”ҹгӮ’дёӯеҝғгҒ«жҠ—иӯ°йҒӢеӢ•гҒҢиө·гҒ“гӮҠгҖҒзҙ„50дәәгҒҢеҸӮеҠ гҒ—гҒҹгҖӮеҠ гҒҲгҒҰгҖҒ11жңҲ11ж—ҘгҒ«гҖҒ1918е№ҙгҒ®еҗҢжңҲеҗҢж—ҘгҒ«з· зөҗгҒ•гӮҢгҒҹпјҲ第дёҖж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢпјүгғүгӮӨгғ„гҒЁйҖЈеҗҲеӣҪгҒ®дј‘жҲҰеҚ”е®ҡгӮ’иЁҳеҝөгҒ—гҒҰгӮ·гғЈгғігӮјгғӘгӮјеӨ§йҖҡгӮҠгҒӢгӮүеҮұж—Ӣй–ҖгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰй«ҳж Ўз”ҹгҖҒеӨ§еӯҰз”ҹгҖҒж•ҷе“ЎгӮүгҒҢеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘгғҮгғўгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒгӮІгӮ·гғҘгӮҝгғқгҒ«йҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгҖҒгҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒ5йҖұй–“гҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰгғ‘гғӘгҒ®гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®й«ҳзӯүж•ҷиӮІж©ҹй–ўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢи¬ӣзҫ©гҒҢзҰҒжӯўгҒ•гӮҢгҒҹпјҲ1940е№ҙ11жңҲ11ж—ҘгҒ®гғҮгғўпјүгҖӮ1940е№ҙ11жңҲд»ҳгҒ§еҲҠиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҺиҮӘз”ұеӨ§еӯҰгҖҸеүөеҲҠеҸ·гҒ§гҒҜгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹдёҖйҖЈгҒ®дәӢ件гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе ұе‘ҠгҒ—гҖҒгғҠгғҒгӮ№гғ»гғүгӮӨгғ„гҒЁгғҙгӮЈгӮ·гғјж”ҝжЁ©гҒ®еҸҚгғҰгғҖгғӨдё»зҫ©пјҲгғҰгғҖгғӨдәәгҒ®ж•ҷе“ЎгӮ’жҺ’йҷӨгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©пјүгӮ’зіҫејҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҺиҮӘз”ұеӨ§еӯҰгҖҸиӘҢгҒҜгӮҪгғӯгғўгғігҒҢз·ЁйӣҶй•·гӮ’еӢҷгӮҒгҖҒгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҢең°дёӢжҙ»еӢ•гӮ’зө„з№”гҒ—гҒҹе…ұз”Је…ҡе№№йғЁгҒЁгҒ®йҖЈзөЎгӮ’жӢ…еҪ“гҖӮгӮёгғ§гғ«гӮёгғҘгғ»гғҮгғҘгғҗгғғгӮҜпјҲGeorges DudachпјүгҒҢеҰ»гӮ·гғЈгғ«гғӯгғғгғҲгғ»гғҮгғ«гғңгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«дәӢеӢҷеұҖгӮ’еӢҷгӮҒгҒҹгҖӮгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒ®еҰ»гғһгӮӨгҒ®гҒ»гҒӢгҖҒгғ©гғігӮёгғҘгғҙгӮЎгғігҒ®еЁҳгҒ§гӮҪгғӯгғўгғігҒ®еҰ»гӮЁгғ¬гғјгғҢгғ»гӮҪгғӯгғўгғіпјқгғ©гғігӮёгғҘгғҙгӮЎгғігҖҒгғҖгғӢгӮЁгғ«гғ»гӮ«гӮөгғҺгғҙгӮЎгҒЁеҪјеҘігҒҢзөҗжҲҗгҒ—гҒҹгғ•гғ©гғігӮ№еҘіжҖ§йҖЈеҗҲпјҲUnion des jeunes filles de FranceпјүгҒ®дјҡе“ЎгҒ®гӮҜгғӯгғҮгӮЈгғјгғҢгғ»гӮ·гғ§гғһпјҲе…ұз”Је…ҡгҒ®ж”ҝ治家гғҙгӮЈгӮҜгғҲгғ«гғ»гғҹгӮ·гғ§гғјгҒ®еҰ»пјүгӮ„гғһгғӘгғјпјқгӮҜгғӯгғјгғүгғ»гғҙгӮЎгӮӨгғӨгғіпјқгӮҜгғјгғҒгғҘгғӘгӮЁпјҲгғқгғјгғ«гғ»гғҙгӮЎгӮӨгғӨгғіпјқгӮҜгғјгғҒгғҘгғӘгӮЁгҒ®еҰ»пјүгӮүгӮӮеҸӮеҠ гҒ—гҒҹгҖӮгҖҺиҮӘз”ұеӨ§еӯҰгҖҸзҙҷгҒҜ1940е№ҙ11жңҲгҒӢгӮү1941е№ҙ12жңҲгҒҫгҒ§гҒ®й–“гҒ«41еҸ·еҲҠиЎҢгҒ•гӮҢгҖҒдәӢе®ҹдёҠгҖҒеӨ§еӯҰж•ҷе“ЎгҒ«гӮҲгӮӢгғ¬гӮёгӮ№гӮҝгғігӮ№йҒӢеӢ•гҒ®ж©ҹй–ўиӘҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҺиҮӘз”ұжҖқжғігҖҸ
1941е№ҙ2жңҲгҒ«гҒҜеҶҚгҒігғүгӮҜгғјгғ«гҖҒгӮҪгғӯгғўгғігҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҺиҮӘз”ұжҖқжғіпјҲLa PensГ©e libreпјүгҖҸгӮ’еүөеҲҠгҒ—гҒҹгҖӮиЎЁзҙҷгҒ«гҒҜгӮІгғјгғҶгҒ®иЁҖи‘үгҖҢгӮӮгҒЈгҒЁе…үгӮ’пјҲMehr LichtпјүгҖҚгӮ’жҺІгҒ’гҒҹгҖӮе•“и’ҷдё»зҫ©гҒ®гғ•гғ©гғігӮ№иӘһ « LumiГЁresпјҲе…үпјүВ» гҒёгҒ®иЁҖеҸҠгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜеүөеҲҠеҸ·гҒ«гғ©гғўгғјпјҲRameauпјүгҒ®еҒҪеҗҚгҒ§гҖҢ20дё–зҙҖгҒ®и’ҷжҳ§дё»зҫ©гҖҚгҒЁйЎҢгҒҷгӮӢиЁҳдәӢгӮ’жҺІијүгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғӯгғјгӮјгғігғҷгғ«гӮҜгҒҢгғ•гғ©гғігӮ№гҒ®дёӢйҷўгҒ§иЎҢгҒЈгҒҹгҖҢ1789е№ҙпјҲгғ•гғ©гғігӮ№йқ©е‘ҪпјүгҒ®зҗҶеҝөгҒ«жұәзқҖгӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢпјҲrГЁglement de comptes avec les idГ©es de 1789пјүгҖҚгҒЁйЎҢгҒҷгӮӢи¬ӣжј”гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҸҚи«–гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҗҢе№ҙжң«гҒ«е°ҸеҶҠеӯҗгҖҺ20дё–зҙҖгҒ®йқ©е‘ҪгҒЁеҸҚйқ©е‘Ҫ - гғӯгғјгӮјгғігғҷгғ«гӮҜж°ҸгҒ®гҖҢйҮ‘гҒЁиЎҖгҖҚгҒёгҒ®еҸҚи«–гҖҸгҒЁгҒ—гҒҰең°дёӢеҮәзүҲгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
1941е№ҙ6жңҲ22ж—ҘгҒ«гғүгӮӨгғ„гҒҢгӮҪйҖЈгҒ«дҫөж”»гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§пјҲзӢ¬гӮҪжҲҰпјүгҖҒзӢ¬гӮҪдёҚеҸҜдҫөжқЎзҙ„гҒҢдәӢе®ҹдёҠз ҙжЈ„гҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҖҒе…ұз”Је…ҡгҒҜ5жңҲгҒ«зөҗжҲҗгҒ—гҒҹеҜҫзӢ¬гғ¬гӮёгӮ№гӮҝгғігӮ№гғ»гӮ°гғ«гғјгғ—гҖҢеӣҪж°‘жҲҰз·ҡгҖҚгӮ’дёӯеҝғгҒ«жң¬ж јзҡ„гҒӘжҠөжҠ—йҒӢеӢ•гӮ’еұ•й–ӢгҒ—гҒҹгҖӮгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜгҖҺиҮӘз”ұжҖқжғігҖҸ第2еҸ·гҒ®еҲҠиЎҢгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҖҒеҚ—д»ҸгҒ®иҮӘз”ұең°еҹҹпјҲгғүгӮӨгғ„и»ҚйқһеҚ й ҳең°еҹҹпјүгҒ«гҒ„гҒҹгӮўгғ©гӮҙгғігҒ®еҚ”еҠӣгӮ’жұӮгӮҒгҒҹгҖӮзҹҘиӯҳдәәгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮе…ұз”Је…ҡе“ЎгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹеҪјгҒ®еҚ”еҠӣгҒҜгҖҒйҒӢеӢ•гҒ®зө„з№”еҢ–гҒ«дёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёҖж–№гҖҒгғүгӮҜгғјгғ«гҒҜгҒ•гӮүгҒ«пјҲеӨ§жҲҰеӢғзҷәгҒҫгҒ§гҖҺж–°гғ•гғ©гғігӮ№и©•и«–гҖҸгҒ®з·ЁйӣҶй•·гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹпјүгӮёгғЈгғігғ»гғқгғјгғ©гғігҒЁгӮӮйӣ‘иӘҢгҒ®ең°дёӢеҮәзүҲгӮ’дәҲе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹпјҲгғүгӮҜгғјгғ«гҒ®еҮҰеҲ‘еҫҢгҒ«гҖҺгғ¬гғғгғҲгғ«гғ»гғ•гғ©гғігӮ»гғјгӮәгҖҸиӘҢгҒЁгҒ—гҒҰеҲҠиЎҢпјүгҖӮгҖҺиҮӘз”ұжҖқжғігҖҸ第2еҸ·гҒҜ1942е№ҙ2жңҲ2ж—ҘгҒ«еҲҠиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮиЎЁзҙҷгҒ«гҒҜгҖҢгғ•гғ©гғігӮ№ж–ҮеӯҰпјҲгғ¬гғғгғҲгғ«гғ»гғ•гғ©гғігӮ»гғјгӮәпјүгҒҢж”»ж’ғгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҖӮгғ•гғ©гғігӮ№ж–ҮеӯҰгӮ’е®ҲгӮҚгҒҶ - еҚ й ҳең°еҹҹгҒ®дҪң家гҒ®еЈ°жҳҺгҖҚгҒЁжӣёгҒӢгӮҢгҖҒе·»й ӯгҒ«гҒҜгҖҢиҮӘз”ұгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®й—ҳгҒ„ - гғ•гғ©гғігӮ№зҹҘиӯҳдәәгҒҢеӣҪж°‘жҲҰз·ҡгӮ’зөҗжҲҗгҖҚгҒЁйЎҢгҒҷгӮӢе®ЈиЁҖж–ҮгҒҢжҺІијүгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
1942е№ҙ2жңҲ15ж—ҘгҖҒгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜеҰ»гғһгӮӨгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гғ‘гғӘ7еҢәгӮ°гғ«гғҚгғ«йҖҡгӮҠгҒ®иҮӘе®…гҒ§гҖҒдё»гҒ«е…ұз”Је…ҡе“ЎгҒ®иҝҪи·Ўгғ»йҖ®жҚ•гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒҷгӮӢгғ‘гғӘиӯҰиҰ–еәҒгҒ®зү№еҲҘзҸӯпјҲBrigades spГ©cialesпјүгҒ«йҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮеҒҪеҗҚгӮ’дҪҝгҒ„гҖҒеҚұйҷәгҒӘгҒҹгӮҒеӨ–еҮәгӮӮгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒ®гӮӮгҒЁгҒ«йЈҹж–ҷгӮ’еұҠгҒ‘гҒ«жқҘгҒҹгғҖгғӢгӮЁгғ«гғ»гӮ«гӮөгғҺгғҙгӮЎгӮӮеҗҢжҷӮгҒ«йҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮзү№еҲҘзҸӯгҒҜгҒ—гҒ°гӮүгҒҸеүҚгҒӢгӮүе…ұз”Је…ҡе“ЎгҒ®иҝҪи·ЎгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒйҖЈзөЎз¶ІгӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгӮҪгғӯгғўгғігҖҒгғүгӮҜгғјгғ«гҒ»гҒӢеӨҡгҒҸгҒ®е…ҡе“ЎгҒҢж•°ж—ҘгҒ®гҒҶгҒЎгҒ«дёҖж–үгҒ«йҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
гғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҒҜ1942е№ҙ3жңҲ20ж—ҘгҒ«гғүгӮӨгғ„и»ҚгҒ«еј•гҒҚжёЎгҒ•гӮҢгҖҒ5жңҲ23ж—ҘгҒ«жҙ»еӢ•гӮ’е…ұгҒ«гҒ—гҒҹгӮҪгғӯгғўгғігҖҒгғҮгғҘгғҗгғғгӮҜгҖҒгӮёгғЈгғіпјқгӮҜгғӯгғјгғүгғ»гғҗгӮҰгӮўгғјпјҲJean-Claude BauerпјүгҖҒгғһгғ«гӮ»гғ«гғ»гӮўгғігӮ°гғӯпјҲMarcel EngrosпјүгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гғўгғігғ»гғҙгӮЎгғ¬гғӘгӮўгғіиҰҒеЎһгҒ§йҠғж®әеҲ‘гҒ«еҮҰгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
и‘—жӣё
- Contre Bergson et quelques autres, Г©crits philosophiques, 1924-1939, Flammarion, 2013 -гҖҺгғҷгғ«гӮҜгӮҪгғігӮүгҒ«жҠ—гҒ—гҒҰ - е“ІеӯҰзҡ„и‘—дҪң 1924-1939е№ҙгҖҸпјҲйӣ‘иӘҢжҺІијүи«–ж–ҮгӮ„ж—ўеҲҠгҒ®и«–йӣҶгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгӮӢи«–ж–ҮгӮ’з·ЁйӣҶпјү
- Friedrich Schelling, Recherches philosophiques sur lвҖҷessence de la libertГ© humaine, 1926 - гғ•гғӘгғјгғүгғӘгғ’гғ»гӮ·гӮ§гғӘгғігӮ°гҒ®гҖҺдәәй–“зҡ„иҮӘз”ұгҒ®жң¬иіӘгҖҸгҒ®гғ•гғ©гғігӮ№иӘһиЁігҖӮ
- Critique des fondements de la psychologie, Гүditions Rieder, 1928В ; Presses universitaires de France, 1967В ; (ж”№йЎҢж–°зүҲ) Critique des fondements de la psychologie. La psychologie et la psychanalyse, Presses universitaires de France, Collection « QuadrigeВ В», 2003 -гҖҺеҝғзҗҶеӯҰгҒ®еҹәзӨҺжү№еҲӨгҖҸ/гҖҺеҝғзҗҶеӯҰгҒ®еҹәзӨҺжү№еҲӨ - еҝғзҗҶеӯҰгҒЁзІҫзҘһеҲҶжһҗгҖҸ
- гҖҺзІҫзҘһеҲҶжһҗгҒ®зөӮз„ү - гғ•гғӯгӮӨгғҲгҒ®еӨўзҗҶи«–жү№еҲӨгҖҸеҜәеҶ…зӨјзӣЈдҝ®гҖҒеҜҢз”°жӯЈдәҢиЁігҖҒдёүе’ҢжӣёзұҚгҖҒ2002е№ҙ
- « La fin d'une parade philosophie Le bergsonismeВ В», Critique des fondements de la psychologie, 1929В ; (ж”№йЎҢж–°зүҲ) Le Bergsonisme, une mystification philosophique, Гүditions sociales, 1947 -гҖҢе“ІеӯҰеӨ©еӣҪгғҷгғ«гӮҜгӮҪгғідё»зҫ©гҒ®зөӮз„үгҖҚ/гҖҺгғҷгғ«гӮҜгӮҪгғідё»зҫ© - е“ІеӯҰзҡ„ж¬әзһһгҖҸ
- Cours de marxisme (1935-1936), Bureau d'Г©ditions, 1936 -гҖҺгғһгғ«гӮҜгӮ№дё»зҫ©и¬ӣеә§гҖҸпјҲеҠҙеғҚеӨ§еӯҰгҒ§гҒ®и¬ӣзҫ©пјү
- Les Grands problГЁmes de la philosophie contemporaine, Bureau d'Г©ditions, 1938 -гҖҺзҸҫд»Је“ІеӯҰгҒ®еӨ§е•ҸйЎҢгҖҸ
- « La Philosophie et les mythesВ В», La PensГ©e, 1939 -гҖҢе“ІеӯҰгҒЁзҘһи©ұгҖҚ
- « La philosophie des lumiГЁres et la pensГ©e moderneВ В», La PensГ©e, 1939 -гҖҢе•“и’ҷдё»зҫ©гҒ®е“ІеӯҰгҒЁиҝ‘д»ЈжҖқжғігҖҚ
- « Qu'est-ce que le rationalismeВ ?В В», La PensГ©e, 1939 -гҖҢеҗҲзҗҶдё»зҫ©гҒЁгҒҜдҪ•гҒӢгҖҚ
- « Dans la cave de l'aveugle, chronique de l'obscurantisme contemporainВ В», La PensГ©e, 1939 -гҖҢзӣІдәәгҒ®жҙһзӘҹгҒ®дёӯгҒ§ - зҸҫд»Ји’ҷжҳ§дё»зҫ©гҒ®жӯҙеҸІгҖҚ
- « La fin de la psychanalyseВ В», La PensГ©e, 1939 гҖҢзІҫзҘһеҲҶжһҗгҒ®зөӮз„үгҖҚпјҲеҒҪеҗҚTh. W. Morrisпјү
- « LвҖҷobscurantisme au XXe siГЁcleВ В», La pensГ©e libre, 1941 -гҖҢ20дё–зҙҖгҒ®и’ҷжҳ§дё»зҫ©гҖҚпјҲең°дёӢеҮәзүҲгҖҒеҒҪеҗҚRameauпјү
- RГ©volution et contre-rГ©volution au XXe siГЁcle, rГ©ponse à « Sang et orВ В» de M. Rosenberg, 1941 -гҖҺ20дё–зҙҖгҒ®йқ©е‘ҪгҒЁеҸҚйқ©е‘Ҫ - гғӯгғјгӮјгғігғҷгғ«гӮҜж°ҸгҒ®гҖҢйҮ‘гҒЁиЎҖгҖҚгҒёгҒ®еҸҚи«–гҖҸпјҲең°дёӢеҮәзүҲпјү
- « AprГЁs la mort de BergsonВ В», La PensГ©e libre, 1941 -гҖҢгғҷгғ«гӮҜгӮҪгғігҒ®жІЎеҫҢгҖҚ
- L'AntisГ©mitisme, le racisme, le problГЁme juif, Гүditions du Parti communiste franГ§ais S. F. I. C., 1941 -гҖҢеҸҚгғҰгғҖгғӨдё»зҫ©гҖҒдәәзЁ®дё»зҫ©гҖҒгғҰгғҖгғӨдәәе•ҸйЎҢгҖҚпјҲең°дёӢеҮәзүҲпјү
- Principes Г©lГ©mentaires de philosophie, Гүditions sociales, 1946, 1954В ; Гүditions Delga, 2008 (еҠҙеғҚеӨ§еӯҰгҒ®еҸ—и¬ӣз”ҹгҒ®гғҺгғјгғҲ1935-1936е№ҙ) -гҖҺе“ІеӯҰгҒ®еҹәжң¬еҺҹзҗҶгҖҸ
- гҖҺе“ІеӯҰе…Ҙй–ҖгҖҸйҷёдә•еӣӣйғҺиЁігҖҒдёүдёҖжӣёжҲҝгҖҒ1952е№ҙгҖҒгҖҲдёүдёҖж–°жӣёгҖү1955е№ҙгҖҒ1964е№ҙгҖҒ1966е№ҙпјҲеүҜйЎҢпјҡиЎҢеӢ•гҒёгҒ®з”ҹгҒҚгҒҹжҢҮйҮқпјүгҖҒ1971е№ҙгҖҒ1974е№ҙ
- 第дёҖйғЁпјҡе“ІеӯҰгҒ®и«ёе•ҸйЎҢ (Les problГЁmes philosophiques)
- еәҸи«– (Introduction)
- 第дёҖз« пјҡе“ІеӯҰгҒ®ж №жң¬е•ҸйЎҢ (Le problГЁme fondamental de la philosophie)
- 第дәҢз« пјҡиҰіеҝөи«– (LвҖҷidГ©alisme)
- 第дёүз« пјҡе”Ҝзү©и«– (Le matГ©rialisme)
- 第еӣӣз« пјҡе”Ҝзү©и«–гҒЁиҰіеҝөи«–гҒЁгҖҒгҒ©гҒЎгӮүгҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гҒӢпјҹ (Qui a raison, lвҖҷidГ©aliste ou le matГ©rialisteВ ?)
- 第дә”з« пјҡ第дёүгҒ®е“ІеӯҰгҒҜгҒӮгӮҠгҒҶгӮӢгҒӢпјҹ дёҚеҸҜзҹҘи«– (Y a-t-il une troisiГЁme philosophieВ ? L'agnosticisme)
- 第дәҢйғЁпјҡе“ІеӯҰзҡ„е”Ҝзү©и«– (Le matГ©rialisme philosophique)
- 第дёҖз« пјҡзү©иіӘгҒЁе”Ҝзү©и«–иҖ… (La matiГЁre et les matГ©rialistes)
- 第дәҢз« пјҡе”Ҝзү©и«–иҖ…гҒЁгҒҜгҒ©гӮ“гҒӘдәәй–“гҒӢпјҹ (Que signifie ГӘtre matГ©rialisteВ ?)
- 第дёүз« пјҡе”Ҝзү©и«–гҒ®жӯ·еҸІ (Histoire du matГ©rialisme)
- 第дёүйғЁпјҡеҪўиҖҢдёҠеӯҰгҒ®з ”究 (Гүtude de la mГ©taphysique)
- 第дёҖз« пјҡгҖҢеҪўиҖҢдёҠеӯҰзҡ„ж–№жі•гҖҚгҒЁгҒҜгҒӘгҒ«гҒӢпјҹ (En quoi consiste la « mГ©thode mГ©taphysiqueВ В»)
- 第еӣӣйғЁпјҡејҒиЁјжі•гҒ®з ”究 (Гүtude de la dialectique)
- 第дёҖз« пјҡејҒиЁјжі•з ”з©¶гҒ®жүӢгҒігҒҚ (Introduction Г lвҖҷГ©tude de la dialectique)
- 第дәҢз« пјҡејҒиЁјжі•гҒ®жі•еүҮ (Les lois de la dialectique) - ејҒиЁјжі•зҡ„еӨүеҢ–пјҲ第дёҖжі•еүҮпјү (PremiГЁre loiВ : le changement dialectique)
- 第дёүз« пјҡзӣёдә’дҪңз”ЁпјҲ第дәҢжі•еүҮпјү (DeuxiГЁme loiВ : lвҖҷaction rГ©ciproque)
- 第еӣӣз« пјҡзҹӣзӣҫпјҲ第дёүжі•еүҮпјү (TroisiГЁme loiВ : la contradiction)
- 第дә”з« пјҡйҮҸгҒӢгӮүиіӘгҒёгҒ®и»ўеҢ–гҖҒгҒҫгҒҹгҒҜйЈӣиәҚгҒ«гӮҲгӮӢзҷәеұ•гҒ®жі•еүҮпјҲ第еӣӣжі•еүҮпјү (QuatriГЁme loiВ : transformation de la quantitГ© en qualitГ© ou loi du progrГЁs par bonds)
- 第дә”йғЁпјҡеҸІзҡ„е”Ҝзү©и«– (Le matГ©rialisme historique)
- 第дёҖз« пјҡжӯҙеҸІгҒ®еҺҹеӢ•еҠӣ (Les forces motrices de lвҖҷHistoire)
- 第дәҢз« пјҡйҡҺзҙҡгӮ„зөҢжёҲжқЎд»¶гҒҜгҒӘгҒ«гҒӢгӮүгҒҶгҒҫгӮҢгӮӢгҒӢпјҹ (DвҖҷoГ№ viennent les classes et les conditions Г©conomiquesВ ?)
- 第е…ӯйғЁпјҡејҒиЁјжі•зҡ„е”Ҝзү©и«–гҒЁгӮӨгғҮгӮӘгғӯгӮ®гғј (Le matГ©rialisme dialectique et les idГ©ologies)
- 第дёҖз« пјҡгӮӨгғҮгӮӘгғӯгӮ®гғјгҒёгҒ®ејҒиЁјжі•зҡ„е”Ҝзү©и«–гҒ®йҒ©з”Ё (Application de la mГ©thode dialectique aux idГ©ologies)
- 第дёҖйғЁпјҡе“ІеӯҰгҒ®и«ёе•ҸйЎҢ (Les problГЁmes philosophiques)
- Principes fondamentaux de philosophie, Гүditions sociales, 1954 (еҠҙеғҚеӨ§еӯҰгҒ®еҸ—и¬ӣз”ҹгҒ®гғҺгғјгғҲ1935-1936е№ҙ) -гҖҺе“ІеӯҰгҒ®ж №жң¬еҺҹзҗҶгҖҸ
- La crise de la psychologie contemporaine, Гүditions sociales, 1947 -гҖҺзҸҫд»ЈеҝғзҗҶеӯҰгҒ®еҚұж©ҹгҖҸ
- Гүcrits, 1. La Philosophie et les Mythes, Гүditions sociales, 1969 -гҖҺи‘—дҪң 1 - е“ІеӯҰгҒЁзҘһи©ұгҖҸ
- Гүcrits, 2. Les Fondements de la psychologie, Гүditions sociales, 1969 -гҖҺи‘—дҪң 2 - еҝғзҗҶеӯҰгҒ®еҹәзӨҺгҖҸ
и„ҡжіЁ
жіЁйҮҲ
еҮәе…ё
еӨ–йғЁгғӘгғігӮҜ
- Georges Politzer, Principes Г©lГ©mentaires de philosophie - гӮёгғ§гғ«гӮёгғҘгғ»гғқгғӘгғ„гӮ§гғ«гҖҺеҝғзҗҶеӯҰгҒ®еҹәзӨҺжү№еҲӨгҖҸ- Marxists Internet ArchiveпјҲгғ•гғ©гғігӮ№иӘһпјү
- POLITZER Georges - MaitronпјҲгғ•гғ©гғігӮ№иӘһпјү
- Paul AlliГЁs, Politzer, un communiste contre le nazisme - MediapartпјҲгғ•гғ©гғігӮ№иӘһпјү
- L'UniversitГ© libre -гҖҺиҮӘз”ұеӨ§еӯҰгҖҸиӘҢ - гғ•гғ©гғігӮ№еӣҪз«ӢеӣіжӣёйӨЁйӣ»еӯҗжӣёзұҚ GallicaпјҲгғ•гғ©гғігӮ№иӘһпјү
- La PensГ©e libre -гҖҺиҮӘз”ұжҖқжғігҖҸиӘҢ - гғ•гғ©гғігӮ№еӣҪз«ӢеӣіжӣёйӨЁйӣ»еӯҗжӣёзұҚ GallicaпјҲгғ•гғ©гғігӮ№иӘһпјү