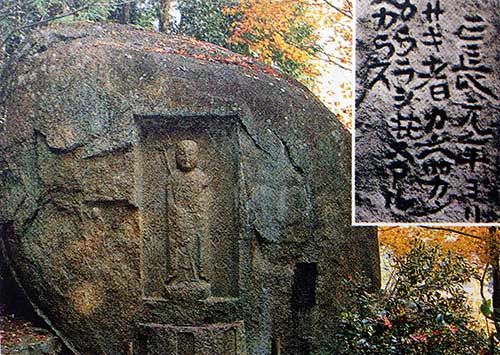播磨の国一揆(はりまのくにいっき)は、室町時代の1429年(正長2年)2月、前年の正長の土一揆の影響を受けて起こった、政治的要求に基づく一揆である。播磨の土一揆(はりまのつちいっき)とも。
播磨国(兵庫県南西部)守護・赤松満祐の配下の軍兵の国外退去、荘園代官の排除を要求して蜂起するが、赤松満祐に鎮圧される。国一揆の始まりとも言われる。
中山定親の『薩戒記』に記述がある。
外部リンク
- 『播磨国一揆』 - コトバンク
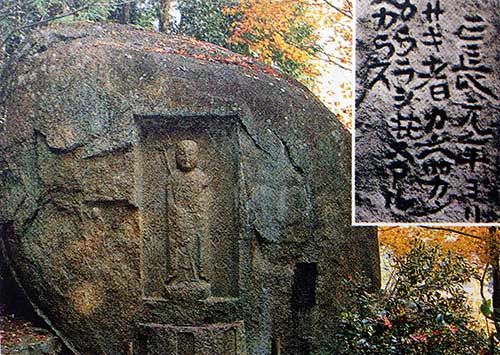




播磨の国一揆(はりまのくにいっき)は、室町時代の1429年(正長2年)2月、前年の正長の土一揆の影響を受けて起こった、政治的要求に基づく一揆である。播磨の土一揆(はりまのつちいっき)とも。
播磨国(兵庫県南西部)守護・赤松満祐の配下の軍兵の国外退去、荘園代官の排除を要求して蜂起するが、赤松満祐に鎮圧される。国一揆の始まりとも言われる。
中山定親の『薩戒記』に記述がある。