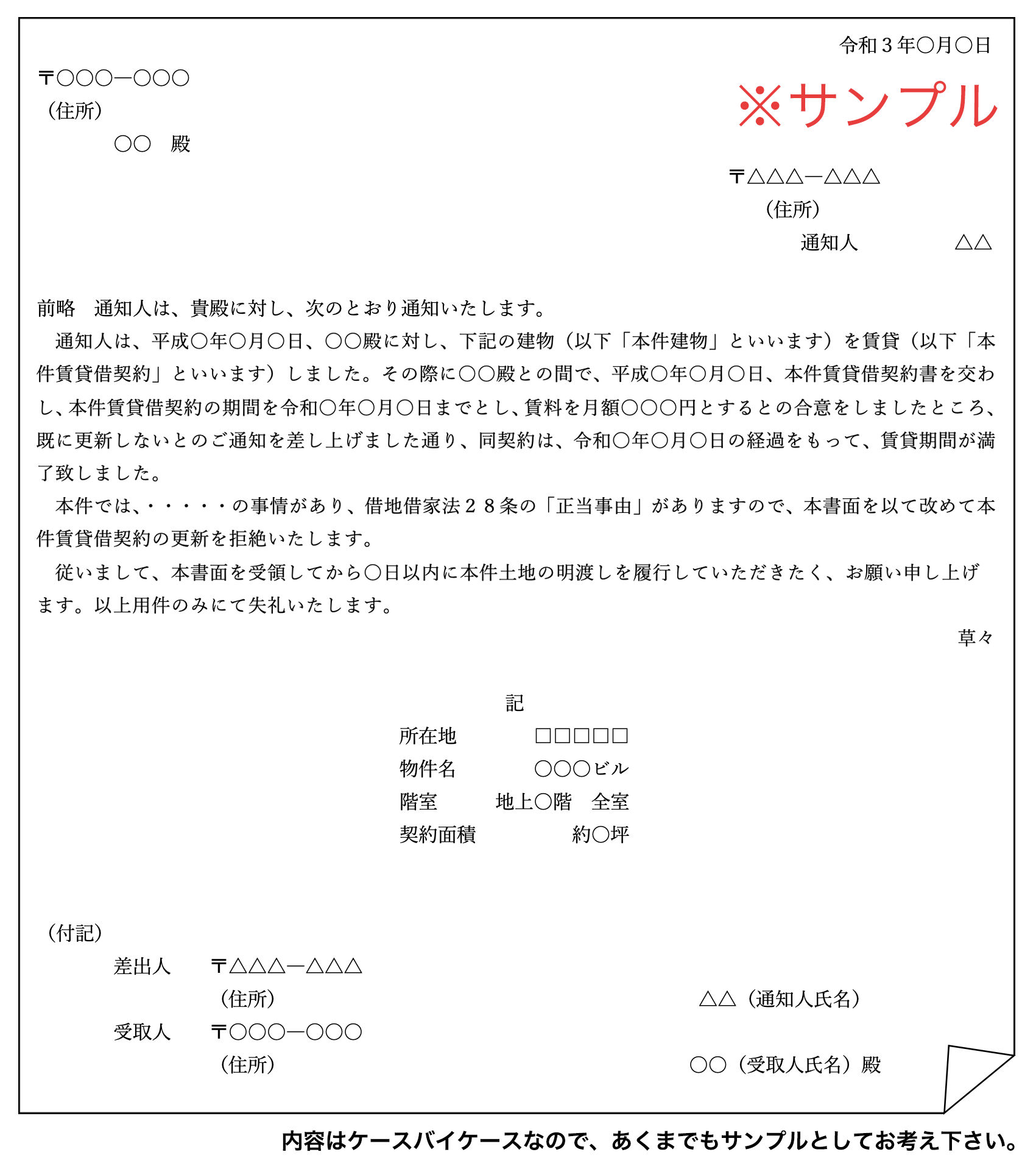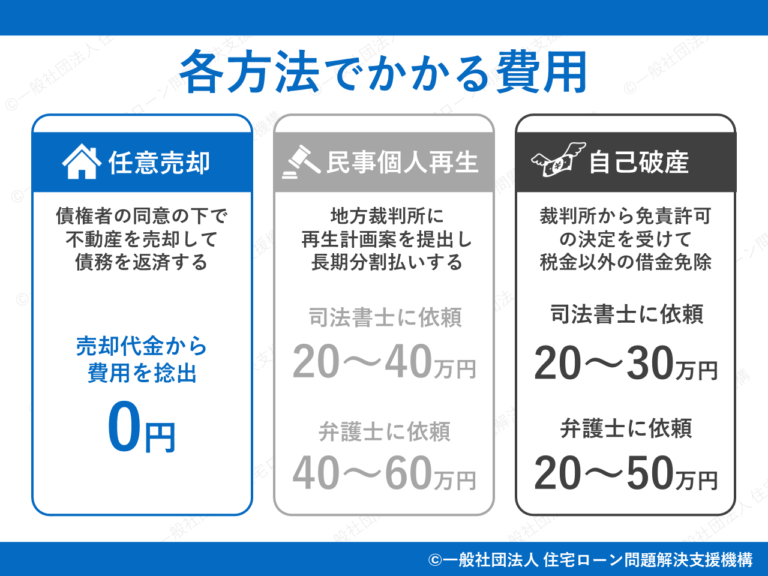дёҚжі•еҚ жңү競売зү©д»¶жҳҺжёЎгҒ—и«ӢжұӮиЁҙиЁҹпјҲгҒөгҒ»гҒҶгҒӣгӮ“гӮҶгҒҶгҒ¶гҒЈгҒ‘гӮ“гҒӮгҒ‘гӮҸгҒҹгҒ—гҒӣгҒ„гҒҚгӮ…гҒҶгҒқгҒ—гӮҮгҒҶпјүгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘дәӢиЁҙиЁҹгҖӮжҠөеҪ“жЁ©иҖ…гҒҢеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢдёҚеӢ•з”ЈгӮ’дёҚжі•еҚ жңүгҒҷгӮӢдәәзү©гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжҳҺгҒ‘жёЎгҒ—иҰҒжұӮгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒҢдәүзӮ№гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
жҰӮиҰҒ
1989е№ҙ11жңҲгҒ«еӣҪж°‘йҮ‘иһҚе…¬еә«гҒҢж„ӣзҹҘзңҢж—ҘйҖІеёӮгҒ®з”·жҖ§гҒ«2800дёҮеҶҶгӮ’иһҚиіҮгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиҝ”жёҲгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеңҹең°гҒЁе»әзү©гҒ®ж №жҠөеҪ“жЁ©гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰ1993е№ҙ9жңҲгҒ«з«¶еЈІгӮ’з”ігҒ—з«ӢгҒҰгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе»әзү©гҒ«гҒҜж №жҠөеҪ“жЁ©иЁӯе®ҡеҫҢгҒ«3е№ҙй–“гҒ®зҹӯжңҹгҒ§иіғиІёеҖҹеҘ‘зҙ„гӮ’зөҗгӮ“гҒ дәәзү©гҒӢгӮүеҸҲиІёгҒ—гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹеӨ«е©ҰгҒҢдҪҸгӮҖгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒе…ҘжңӯеёҢжңӣиҖ…гҒҢеҮәгҒҡгҖҒеӣҪж°‘йҮ‘иһҚе…¬еә«гҒҢе»әзү©гҒ®жҳҺгҒ‘жёЎгҒ—гӮ’жұӮгӮҒгҒҰжҸҗиЁҙгҒ—гҒҹгҖӮ
1995е№ҙ10жңҲгҒ®еҗҚеҸӨеұӢең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖгҖҒ1996е№ҙ5жңҲ29ж—ҘгҒ®еҗҚеҸӨеұӢй«ҳзӯүиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨжұәгҒҜгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒеӨ«е©ҰгҒҜжЁ©йҷҗгҒ®гҒӘгҒ„дәәгҒӢгӮүиІёеҖҹгҒ—гҒҹдёҚжі•еҚ жңүиҖ…гҒЁиӘҚе®ҡгҒ—гҒҰгҖҒжҳҺгҒ‘жёЎгҒ—гӮ’е‘ҪгҒҳгҖҒеӨ«е©ҰгҒҜдёҠе‘ҠгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒеӨ«е©ҰгҒҜжҳҺгҒ‘жёЎгҒ—гҒ«еҝңгҒҳгҒҹгҒҢгҖҒиЁҙиЁҹгҒҜз¶ҷз¶ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
1999е№ҙ11жңҲ24ж—ҘгҒ«жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖеӨ§жі•е»·гҒҜжҠөеҪ“жЁ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҢдёҚеӢ•з”ЈгҒ®дәӨжҸӣдҫЎеҖӨгҒӢгӮүд»–гҒ®еӮөжЁ©иҖ…гҒ«е„Әе…ҲгҒ—гҒҰејҒжёҲгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢжЁ©еҲ©гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҠөеҪ“жЁ©иҖ…гҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдёҚеӢ•з”ЈгҒ®дҪҝз”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе№ІжёүгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒҷгӮӢеҺҹеүҮгӮ’зӨәгҒҷдёҖж–№гҒ§гҖҢдёҚжі•еҚ жңүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҒ©жӯЈгҒӘдҫЎж јгӮҲгӮҠеЈІеҚҙдҫЎж јгҒҢдёӢиҗҪгҒҷгӮӢжҒҗгӮҢгҒҢгҒӮгӮӢгҒӘгҒ©жҠөеҪ“жЁ©иҖ…гҒ®ејҒжёҲи«ӢжұӮжЁ©гҒ®иЎҢдҪҝгҒҢеӣ°йӣЈгҒ«гҒӘгӮӢжҷӮгҒҜжҠөеҪ“жЁ©дҫөе®ігҒ«гҒӮгҒҹгӮӢгҖҚгҒЁгҒ—гҖҒжҠөеҪ“жЁ©гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰжҳҺгҒ‘жёЎгҒ—гӮ’и«ӢжұӮгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжұәгҒҜгҖҒжҠөеҪ“жЁ©иҖ…гҒҜжүҖжңүиҖ…гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰзү©д»¶гӮ’йҒ©еҲҮгҒ«з¶ӯжҢҒгҖҒдҝқеӯҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жұӮгӮҒгӮӢжЁ©еҲ©гӮӮгҒӮгӮӢгҒЁгҒҷгӮӢж–°еҲӨж–ӯгӮ’зӨәгҒ—гҒҹгҖӮеҘҘз”°жҳҢйҒ“еҲӨдәӢгҒҜ競売申гҒ—з«ӢгҒҰд»ҘеүҚгҒ§гӮӮзү©д»¶гҒ®дҫЎеҖӨгӮ’дёӢгҒ’гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘиЎҢзӮәгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҢдҫөе®ігӮ’йҳ»жӯўгҒҷгӮӢжі•зҡ„жүӢж®өгҒҢз”Ёж„ҸгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁиЈңи¶іж„ҸиҰӢгӮ’иҝ°гҒ№гҒҹгҖӮ
йҒҺеҺ»гҒ®еҲӨдҫӢ
еӨ§йҳӘеёӮгҒ§гҒ®еҗҢзЁ®гҒ®дәӢжЎҲгҒ®1991е№ҙ3жңҲ22ж—ҘгҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжұәгҒ§гҒҜгҖҢдёҚжі•еҚ жңүиҖ…гҒҢгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒ競売зү©д»¶гӮ’иіје…ҘгҒ—гҒҹдәәгҒҢж°‘дәӢеҹ·иЎҢжі•гҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгҒ«еҫ“гҒЈгҒҰеј•гҒҚжёЎгҒ—гӮ’жұӮгӮҒгӮӢзӯүгҒ®иЈҒеҲӨгӮ’иө·гҒ“гҒҷгҒ“гҒЁгҒ§еҚ жңүгӮ’жҺ’йҷӨгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеҚ жңүгҒқгӮҢиҮӘдҪ“гҒҜдёҚеӢ•з”ЈгҒ®жӢ…дҝқдҫЎеҖӨгӮ’дёӢгҒ’гӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ—гҖҒжҠөеҪ“жЁ©гҒҜеҚ жңүгӮ’жҺ’йҷӨгҒ§гҒҚгҒҡжүҖжңүиҖ…гҒ«д»ЈгӮҸгҒЈгҒҰжҳҺгҒ‘жёЎгҒ—гӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒҷгӮӢеҲӨж–ӯгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒҜиіғиІёгғһгғігӮ·гғ§гғігҒ®дёҖиҲ¬еұ…дҪҸиҖ…гҒҢжҠөеҪ“жЁ©иҖ…гҒ®йғҪеҗҲгҒ§зӘҒ然йҖҖеҺ»гҒ•гҒӣгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘдәӢж…ӢгҒҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҖҒжҠөеҪ“жЁ©иҖ…гҒ®жЁ©еҲ©гӮ’гҒ„гҒҹгҒҡгӮүгҒ«жӢЎеӨ§гҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶж°‘жі•дёҠгҒ®й…Қж…®гҒҢеғҚгҒ„гҒҹгҒЁжҺЁжё¬гҒ•гӮҢгҒҹгҒҢгҖҒзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰеҚ жңүеұӢгҒ®и·ӢжүҲгӮ’жӢӣгҒҚгҖҒжҠөеҪ“жЁ©иҖ…гҒ§гҒӮгӮӢйҮ‘иһҚж©ҹй–ўгҒҜеҜҫеҝңгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒгғҗгғ–гғ«еҙ©еЈҠеҫҢгҒ®ж—Ҙжң¬гҒ®йҮ‘иһҚжҘӯз•ҢгҒ®иЎ°йҖҖгҒ«жӢҚи»ҠгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҹгҖӮж°‘дәӢеҹ·иЎҢжі•гҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгҒ§еҚ жңүеұӢгӮ’иҝҪгҒ„еҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҹ·иЎҢжүӢз¶ҡгҒҚгҒ«гҒҜ競売зү©д»¶гӮ’иіје…ҘгҒ—гҒҹдәәгҒҢеҚұйҷәгӮ’жүҝзҹҘгҒ®дёҠгҒ§иҮӘеҲҶгҒ§иЈҒеҲӨжүҖгҒ«з”ігҒ—з«ӢгҒҰгҒҰиЎҢгҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзҸҫе®ҹгҒ«гҒҜеҚ жңүеұӢгҒҢеұ…еә§гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«зү©д»¶гӮ’иҗҪжңӯгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢеёҢжңӣиҖ…гҒҢгҒҫгҒҡзҸҫгӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒҢе®ҹж…ӢгҒ гҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒ1991е№ҙгҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжұәгҒҜгҖҢзү©д»¶гҒҢеЈІгӮҢгҒҡгҒ«дҫЎеҖӨгҒҢдёӢгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзҸҫе®ҹгҒЁд№–йӣўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжү№еҲӨгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
и„ҡжіЁ