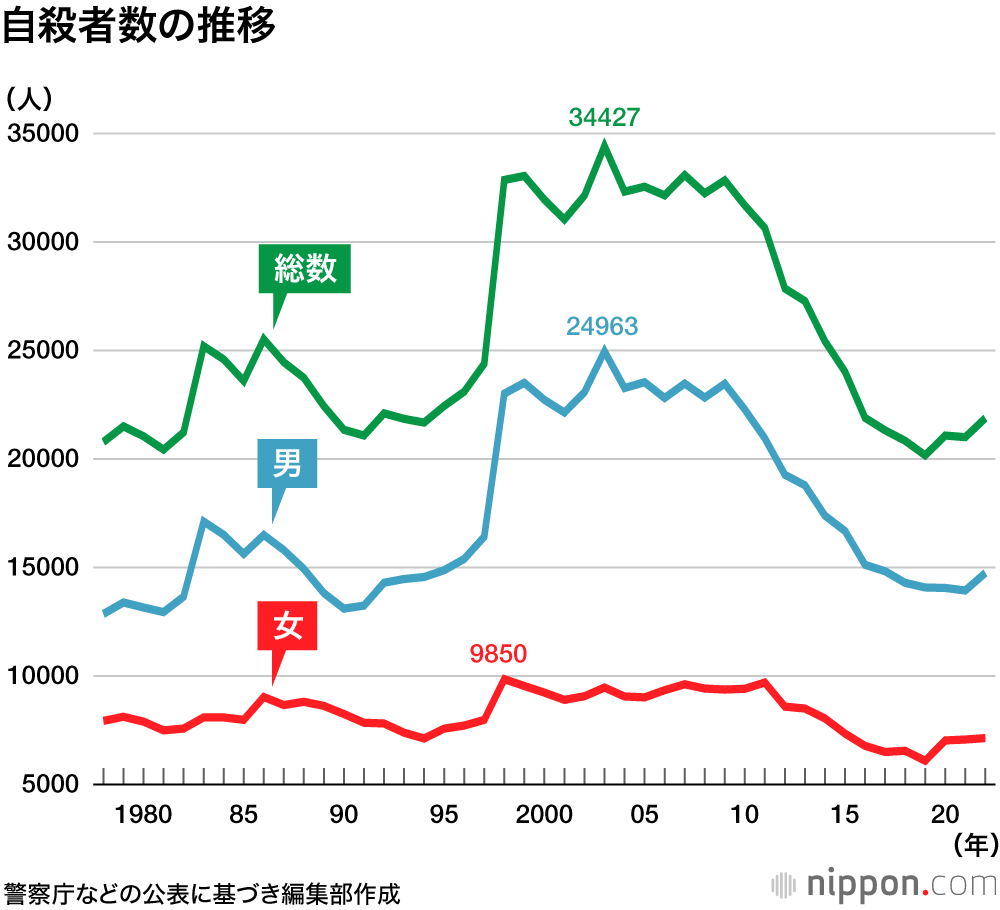操縦者による自殺(そうじゅうしゃによるじさつ)とは、免許を持っているかどうかに関わらず、航空機の操縦者が、自殺を目的に、故意に航空機を墜落させたり、自爆させたりすることである。同乗している乗客や、墜落地点の人々を巻き添えに殺害することもある。この場合、殺人自殺と表現される。
航空機の歴史の中で、航空事故は数多く起こっているが、このうちいくつかは操縦者による自殺が疑われており、またいくつかは実際に自殺が目的であったと断定されている。しかし、一般に、事故の捜査官が操縦者の自殺の動機を特定することは困難である。これは、操縦者が故意にボイスレコーダーやトランスポンダといった記録装置の電源を切ることが多く、捜査を妨害する事例があるからだ。その結果、操縦者の自殺を確実に証明することは困難となっている。
操縦者が自殺を意図していたことを示す「説得力のある証拠」がない限り、捜査官は航空機事故を自殺として認定しない。「説得力のある証拠」とは、例えば、過去に自殺未遂を起こしていた記録や、自殺をほのめかす発言、私生活で問題のある言動(借金を抱えている、家族関係が悪化しているなど)が認められる場合、遺書の存在、精神障害の病歴などが含まれる。2002年から2013年までの操縦者による自殺の調査を行ったところ、自殺した可能性のある事例が5つ、明確な自殺であると判定された事例が8つ、報告された。事故の調査官は、テロの専門家と協力して、操縦者が過激派グループと接触していたかどうかも調査し、自殺の目的が、テロ行為であったかどうかを判断しようとする場合もある。
操縦者による自殺のほとんどが軽飛行機で実行される。軽飛行機が1人でも操縦できること、小回りがきいて操縦しやすいことからよく選ばれる。この場合、基本的に他の乗客を巻き添えにすることはないが、市街地に墜落すると地上の住民を巻き添えにする危険がある。そして、自殺が疑われる事故事例の半分で、操縦者は飛行時には禁止されている薬物や、アルコール、抗うつ薬を使用していた。これらの操縦者の多くは、精神病歴を有していたが、規制当局にはその病歴を隠していた。
第二次世界大戦の自爆攻撃
第二次世界大戦では、いくつかの国で、操縦者による自爆攻撃が実施されている。
ソビエト連邦の飛行士ニコライ・ガステロは、戦闘中に撃墜されたが、このとき、機体はまだ制御可能であったとされる。しかし、彼は地上に係留中の敵機に体当たりを実施し、「自爆攻撃」を行った。いくつかの論争はあるが、彼は敵に自爆攻撃をした最初のソ連飛行士と信じられている。
その後、戦争中では連合国軍、枢軸国軍を問わず、自殺を前提にした攻撃が増えた。最もよく知られているのは、第二次世界大戦の終結間際に、連合国艦艇に対する大日本帝国陸海軍からの攻撃である。これらの攻撃は「神風特別攻撃隊」と呼ばれ、従来の魚雷や爆弾による攻撃よりも、効果的に連合国の軍艦を撃沈、あるいは大破させた。1944年10月から1945年の間に、約3,860人の日本軍飛行士が、この方法で死に至った。
自殺目的またはその疑惑がある事故の一覧
このリストには、第二次世界大戦における自爆攻撃は含まれていない。
確度
操縦士により引き起こされた事故
ハイジャックによる事故の一覧
発表された研究
エアロスペース・メディスン・アンド・ヒューマンパフォーマンスにおいて、2016年に発表された研究では、航空機が関与する自殺および、巻き添えによる殺人を体系的に調査している。調査官達は、「航空医学の文献や、メディアでは「自殺」と「巻き添えによる殺人」の両方を「操縦者による自殺」と表現している。しかし、精神医学では、異なる危険因子を持つ別個の出来事と考えられている」と指摘している。この研究は、1999年から2015年の航空機事故を対象としている。医療データベース、インターネット検索エンジン、および航空安全データベースを調査し、(同期間の195件の航空機事故に対して)自殺は65件、航空機から乗客が飛び降りた事例の6件を含めている。また、このうち18件は、合計732人の死者を含む殺人自殺であった。うち、操縦者が乗客を巻き添えにした事例は、13件であった。この研究によると、バスや電車など、航空以外の事例と比較すると、航空機では操縦者による自殺における殺人自殺の割合が、17%ほど大きかった。
調査官のケネディは、航空機を利用した自殺および殺人自殺は、極稀にしか発生しないものの、地上における事故と比較した場合、巻き添えとなる死亡者が多くなることから、その社会的な影響は、大きくなると述べている。この調査では、以下の点が指摘された。
- メディアが自殺または殺人自殺を報道した後、操縦士による自殺が連続して発生するクラスター化の証拠がある(模倣犯が多発する)。
- 民間旅客機の操縦者による6件の自殺(および殺人)のうち、5件は、操縦者はコックピットに放置された後に発生した。一方、6件目の日本航空の事故(日本航空350便墜落事故)では、機長が操縦桿を押し込んで自殺を試みるも、コックピットにいた副操縦士が阻止に動いたことで、結果的に墜落はしたものの、その衝撃を和らげる事になり、150人の命が救われた。この事例は、コックピットに2人の操縦士がいることで、自殺は未然に防げる、あるいは被害を軽減できると示唆している。
- 自殺または殺人自殺のリスクに関連する単一の要因はなかった。両方の事例に関連する要因には、操縦者が有している法的なトラブル、金銭的問題、職場での悩み、精神障害、および人間関係によるストレスが含まれている。自殺のほぼ半分では、薬物やアルコールの影響が見られた。しかし、これらは、殺人自殺では影響が見られなかった。
防止
アメリカの規制では、安全上の理由から、少なくとも2人の乗務員が常にコックピットにいる必要があるとされている。これは、医療やその他の緊急事態に対応できるようにするためであり、その中には誰かが飛行機を墜落させようとした場合の阻止も含まれる。
一部のヨーロッパ諸国とカナダ、オーストラリア、日本では、2015年3月24日のジャーマンウイングス9525便の墜落を受けて、50席以上の旅客座席を備えた航空機では、コックピットに常に2人が常駐しなければならないという規則を定めた。
脚注
関連項目
- 航空事故
- 航空機ハイジャック事件の一覧
- 神風特別攻撃隊
- 乗物による突入攻撃
- 警察による自殺
外部リンク
- 意図的な行為: cnn.comで意図的に墜落したパイロットの5つのケース
- aviation-safety.netのパイロットによって意図的に引き起こされた航空機事故および事故のリスト
- canberratimes.comでのパイロット自殺事件の数は少ない